先軫(せん・しん)
先軫は晋の大夫で、原を食邑としたので原軫とも呼ばれます。背景を言っておきますと春秋の初期のこと、楚の勢いというのがやたらと強い時期がありまして西方東方を圧しました。楚の文王の時には北は黄河流域にまで発展、申とか息とか鄧とか、そのへんを切り取ってガハハとか言ってたわけです。伝統ある蔡もこれに屈服、楚の成王の時には有名な斉の桓公、この人が中原の覇王を称していたわけですが、楚は斉の威徳に靡かず、さらに北に伸び東に延びていきまして、斉の国威が衰えると一気に北上、魯、宋、鄭、蔡、曹、衛といった中小国を併呑します。周の襄王の14年(前638年)、楚軍は泓水の戦いで宋の襄公に重傷を負わせて破り、ついに中原に進出しました。
で、このとき山西地方の南にあって力を蓄えていたのが晋。献公、惠公のときにいろいろと社会改革をやりまして、献公は軍を三軍をそれぞけ上下二軍編成にし、惠公は生産促進のために“作愛田”、兵源確保のために“作州兵”という改革を打ち出しました。これによって晋が中原の覇王となるための準備を固め、でもって泓水の戦いから2年後の周の襄王16年(前636年)、19年間諸国を流亡していた公子、重耳が帰国、即位してこれが晋の文公となりました。文公は流浪の時、先軫をはじめとして趙衰、狐偃といった面々にたすけられておりまして、だから即位すると先軫たちを重臣として遇します。で、頭の明敏だった文公は中原に覇を唱えるためにはまず楚をぶっ倒す必要があると確信したわけですがまだ力が足りない。というわけで国内的には富国強兵を進めつつ、国外的には西に秦、東に斉と同盟を結びました。
そんなおりに転機がおとずれたのが文公の四年。楚は斉の国境を圧迫し、さらに大挙して宋を囲みました。このとき宋から晋にやってきた使者を公孫固といいますが、まあこの人の名前は重要じゃないです。省いて書かれてる書物もあるぐらいで、まあはっきり言って端役です。そんでこのとき膝を打って喜んだのが先軫。文侯に向かって「これは絶好の機会でございます。宋、斉に救いをもたらして患いを除き、威をもって覇を定めましょう」と言いました。ただ富国強兵に努めたとはいえまだ楚と晋の国力はかなり違います。しかも楚には脅迫して同盟国とした国がたっぷりとあってこれもアドバンテージになっていました。さらに言えば宋と晋はすぐ隣につながっている国というわけでもない、助けようと思えば必ず楚の同盟国――というか実際は属国みたいなもんですが――の曹と衛を通らなければならないというわけで文公も二の足を踏みます。もともと慎重に慎重を期すタイプの文公ですからこれもやむなし。しかしここで狐偃が一計を案じました。つまり、曹と衛を通らなければならないのではなく、曹と衛を叩いてしまえばおのずと宋の囲みは解かれる、というわけです。狐偃の言葉によれば「楚ははじめ曹を得てまた新たに衛と婚姻を結んだものです。よってわれわれが曹と衛を討てば、楚はかならずそれを救いに来るでしょう。そうすればおのずと宋は救われる事になります」とまあ、そういうことになります。文侯もそれならオッケーということで献策を容れまして、三軍を編成、中軍の元帥に郤縠、中軍の佐に郤溱、上軍の将に狐毛、その佐に狐偃、下軍の将に欒枝、先軫をその佐として、前632年、晋軍はまず曹を討たんとします。で、その途中にある衛が道を貸さない。これはもちろん織り込み済みのことで、「それならお前んトコも潰してやるぁ」ということですね。かくて曹と衛を攻めた晋軍は正月に五鹿を取りますが、翌2月、元帥たる郤縠が死んでしまいます。だから軍を引くか、といったら引かずに、なんと下軍の佐にすぎなかった先軫が一躍中軍の将に抜擢されるのです。で、斉侯と欽孟で盟約を結んだ晋軍はまず衛の地を平定、3月には曹に入り、曹の共公をとらえました。これによって晋は宋と国境を隣にします。
晋が曹、衛両国を占拠すると、楚軍はかえって全力で宋の都・商丘を攻撃しました。狐偃としては策が外れたことになります。宋はまた晋に危急を告げますが、文公は「宋は急を告げてきたが、私はこれを救おうと思わない。宋は必定、楚に降って晋と断交するであろうからだ。楚に使いを送って宋を攻めないよう説得しようとも思ったが、楚は聞き入れないだろう。思うに楚と一戦するには中原の国がともに轡を並べねばならぬ。しかし秦や斉はどちらも傍観していて助けを出さない。これではいかんともしがたかろう?」といって渋ります。このとき先軫が「それならば妙案があります。まず宋から斉、秦に賄賂を贈らせ、利をもって彼らに楚が撤兵するよう説かせればよろしい。同時にわれらは再び曹の国君を拘留し、衛の一部を宋に分かち与え、もって楚への徹底抗戦の意思を堅固なものとするのです。楚にとって曹と衛の保衛は絶対、必ず斉、秦の撤退勧告をはねつけるでしょう。斉と秦は宋から賄賂を受け取っているのですから、楚が聞き入れないとなれば必定、戦わざるわけにはいかなくなります」と軍略家らしいところを説きました。文公はこれを聞き入れて従い、はたして楚の成王は斉、秦両国の調停を退けました。斉、秦両国はついにやむなく楚との交戦に踏み切ります。ここに晋、斉、秦の三強国による対楚連盟が結成されたわけです。
楚の成王は斉、秦が晋と連合したことを見て取ると、形勢不利とみて一方で楚軍を撤退させ、他方、統帥の子玉に晋との交戦を避けるよう命じます。成王は子玉を戒めて曰く「晋侯は流浪すること19年、経験豊富であり、民情を洞察する力に長けている。軽挙妄動してはならんぞ」と言ったのですが、なにぶん子玉はプライドが高くやや傲岸な人物でありましたから、晋の実情を知ることもせず、楚王の命に反して晋軍と交戦に入ります。楚王はやむなく彼の請求に応じて兵力を加増し、西広、東宮(楚の軍制のことだそうですが、詳しいことは不明)と若敖の六軍を増援に送りました。で、子玉が晋軍との決戦を前に宛春に使者を送り、文公に向かって「晋が曹と衛を解放するのであれば、楚は宋への囲みを解こう」と停戦条件を出します。狐偃は子玉の無礼に怒りを覚えながらも宋の囲みが解かれるならと曹、衛両国を放棄しようと提議しますが、先軫はこれに反対、子玉の言を「一言にして三国を定めんとする」ものとして退けます。このために宋が楚によって滅ぼされたなら晋は宋を救わんとして結局これを滅亡させた謗りを各国から受けることになりますが、先軫はすでに対策を提出しておりました。「私に(周王朝の許可を得ず、ということです)曹、衛を許し、楚から離反させるがよろしい。楚が怒って宛春をとろうとしてくれば、すでに勝ちは決まったようなものです」と。そこで文公は拘留していた曹、衛の両国君を私に許し、両国を復国させました。曹、衛両国は晋に恩義を感じて楚と断交、子玉は果たして怒り狂い、晋軍の誘いに乗るなという成王の告誡を顧みず曹の都・陶丘に軍を進めます。子玉は楚の名将で彼が死んだとき晋の文公は手を打って大いに喜んだ、ということですが、このさまを見るとただの猪ですね。文公は楚軍が迫るとかつて流浪時代に楚から受けた恩に応え、軍を三舎(30里)退かせます。“三舎を退く”というと美談として伝わっていますが、これは実のところを言えば敵に自分たちの怯懦を見せて驕らせる策略だったと思われます。すくなくとも子玉はこれに乗って嵩にかかって攻めたてようとします。
4月2日、晋、斉、秦、宋の軍は城濮に集結します。4日、城濮以南の有莘で楚軍と対陣、決戦の火ぶたが切って落されました。晋の左翼は下軍の佐将・胥臣。これが戦車の馬上に虎の皮をかぶせて軍威を助長し、楚の右軍である陳、蔡両軍に突撃を敢行します。陳、蔡両軍は晋軍の戦闘力の前に一撃で壊乱、度を失って退却しました。晋の右軍は上軍の主将・狐毛で、大旗を両面に押し立てて主将後退を装い、楚の左軍を誘い出すことに成功。下軍の主将・欒枝は車で木の枝を曳いて砂埃を立て、撤退したと見せかけて敵の右軍を誘い出します。子玉は実情を悟ることなく勝ったと思い込み、全軍に追撃を命じました。子玉率いる左軍はあまり迅速に進んだ結果孤軍突出してしまい、挟撃の格好のターゲットとなります。ここまですべて先軫の読み通りでした。先軫はこれを撃ち、また晋の貴族の子弟により編成される精鋭部隊を指揮して楚の左軍右翼を崩します。このときとばかり偽装撤退していた晋軍は転進、逆撃に転じ、中軍と合して楚の左軍を挟撃、そのほとんどを殲滅しました。子玉は左右の軍を見るもみな敗北、銅鑼を鳴らして軍を収集し戦場から退出します。晋軍の赫々たる大勝利で、その要因はやはり先軫の巧緻な戦術に帰するというべきでしょう。先軫は敵の主帥に驕慢にして敵を軽んじる癖があるのを見て取り、強きを避けて弱きを撃ち、偽装撤退を使っていよいよ敵を驕らせ、しかるのちに各個撃破するという戦法で勝ちを制したわけです。
4月29日、晋の文公は鄭の践土に諸侯を招集して盟を会し、周の襄王に楚の捕虜1000人と戦車100乗を献じました。襄王は文公を諸侯の長である侯伯となし、ここに晋の覇業が確立されます。もちろんこれは城濮の大勝利を受けての事であり、これを文公の覇業において先軫を抜きに語るわけにはいきません。「城濮の事は先軫の謀なり」というのは誇大ではないのです。
前627年、文公は世を去ります。秦国は文公の喪に乗じて兵を発し、鄭国を襲いました。先軫は新たに即位した晋の襄公に向かい、「秦は蹇叔の遺命に背き、貪婪を行い百姓を働かせております。これは天がわれらに与えた好機と見るべきでしょう。この機会を逸さざれば、敵人逃げることあたわず。敵を放置しておけば早晩、禍をなすでしょう。天意にたがわず吉利を取りたまえ。秦に軍を進めるのです」と説きました。しかし欒枝は「秦には文公の即位を支持してもらった恩があります。それを忘れて軍を進めるのは先君の遺命に背くことになるのでは?」と反対、これに対し先軫は「秦はわれらの喪時に悲傷を示さず、どころか我が国と同姓の国を攻めたのであるから、礼を失したのは彼らの方であろう。先君のうけた恩施というが、私が聞くに『一日敵を放っておけば、数世の患いを残す』という。子孫後代のことを考えるなら、先君の遺命がなにするものであろう?」と答え、襄公は先軫を支持して軍隊を動員しました。襄公は黒い喪服を身にまとって出征し、4月13日、秦軍が鄭を襲った帰路、殽の隘路に伏兵を埋伏させました。もちろん指揮を執ったのは襄公ではなく先軫です。この戦いで晋軍は秦軍を全滅させ、百里孟明子視、西乞術、白乙丙らの将帥を捕えました。殽の戦いにおける勝利で晋は秦の中原進出を阻んだといえます。
文公夫人はもともと秦の穆公の娘で、襄公の生母です。彼女は殽の戦いでとらえた三将を釈放帰国させることを襄公に請い、襄公もこれに応じたのですが、これに怒ったのが先軫でした。朝見すると襄公に詰め寄り、襄公が「母の頼みだったから仕方がないのだ」と答えると憤激して「武将が気力を尽くしてようやく戦場に彼らを捕えたというのに、婦人の言を聞き入れてこれを赦免するとは。これでは折角の戦果が毀れ敵の士気を高めてしまいます。晋が滅ぶのもそう遠いことではないでしょう」といって地に唾を吐き捨てました。先軫は怒りのあまりに襄公の母を“婦人”と卑しくののしり、唾を吐いたわけですが、これがまずかった。襄公は先軫をとがめませんでしたが、先軫はこれを後悔します。
同年秋、狄軍が晋に攻め込み、箕の地を占拠しました。8月22日、晋侯は箕の地で狄を打ち破りましたが、主君を面罵して辱めたことを後悔していた先軫は「匹夫志たくましくして、君が我を討たぬならあえて自らを討たん!」と叫んで兜を脱ぎ捨て敵中に突撃、壮絶な討死を遂げます。狄人は彼の首級を晋に送還しましたが、その顔はまるで生きているようだった、といいます。

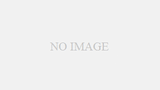
コメント