エピロス国王。体験した主要な戦争はデミトリウスとの戦争(前二九五―二八四)、ロ―マとの戦争(前二八一―二七二、二七六―二七五)、カルタゴとのシシリ―作戦(前二七八―二七六)など。主な作戦はイプソス(前三〇一)、ヘラクレア(シャンサノ近郊。前二八〇)、アスクュルム(アスコリ・サトリア―ノ。前二七九)、ベネヴェントゥム(ベネヴェント。前二七五)等々。
紀元前三一九年生まれ。マケドニアのアレクサンダ―大王とは縁戚関係に当たる。エペロスの王となったのは一二歳の時(前三〇七)、デミトリウス一世と連合しマケドニアの包囲軍を率いるが失敗、退位させられてアジアに逃れ、そこでデミトリウスおよびアンティゴノス一世の二人と合流、彼らとともにイプソスの戦いを経た。彼はアレクサンダ―の戦術を模倣して敢闘するも戦争全体は敗北、ピュロスはデミトリウスとプトレマイオス一世の間の取り決めによってプトレマイオスのもとで人質となるが、のち彼はプトレマイオスとの間に友誼を結び、彼の助けを得て王国の主に復帰する(前二九七)。最初彼は同権君主として同族のネオプトレムス二世と共同統治したが、まもなく彼を暗殺(前二九六)、マケドニア内訌の混沌情勢に乗じ、ギリシア方面へ力尽くで彼の王国を広げた。デミトリウスとの間にしばしば作戦を起こし中央ギリシアおよびマケドニアの覇権を争い(前二九五―二八五)、タレントゥム(タ―ラント)の誘いに応え二万五千の軍勢(加えて二〇頭の戦象)を率いてイタリアに上陸(前二八一)、ロ―マ軍をヘラクレアの戦い(前二八〇)にて破るも、この戦いにおける彼の損害もかなりなものにのぼった。人々が彼の成功を喜んでいたとき、彼本人は次の戦いを想定して「もしもう一度戦えば、勝ちを得ても我が軍はすっかり消滅するだろう」と慨嘆した。後世、このように実り少ない行為をさして、俗に‘ピュロスの勝利’と呼ぶ。しかしなお、彼は前進してロ―マに向かった。ロ―マ人は決着を決意し、彼らは同盟と引退者を総動員して南イタリアに集結させ、より軍隊の士気を高めた。ピュロスは他に想像もつかないような奇策でアスクュルムの戦いに勝利した(前二七九)が、彼の負傷兵たちもきわめて多数に上り、気落ちした彼はロ―マと戦う努力を蜂起、シチリア人からシシリ―地方のカルタゴ人平定を依頼されてこれを受諾、カルタゴを包囲攻撃(前二七八)する。幾ばくかの成功にもかかわらずカルタゴ人を根絶できないと悟るや、彼は塞外から中央および西シシリ―に入ってここを自らの版図とした(前二七七―二七六)。カルタゴはロ―マと急遽同盟関係を結び、ピュロスをイタリアに追い返した。帰還したピュロスは大いなる脅威と呼ばれたが、ベネヴェントゥムの戦いでM・カリウス・デンタトゥス率いるロ―マ軍の前に敗北する。誰かがピュロスを謗って、「ご自慢の象たちが後退し、ピュロスは永眠する」といい、その軍は大恐慌に陥った(前二七五)。大損害を蒙ってピュロスはエピロスに帰り、伝えられるところではこう述べたという。「ロ―マとカルタゴはどんなにか立派な戦場であったが、私はここに帰ってきた」。彼はアンティゴノス二世ゴナトゥスとともにテッサロキアに上陸、港湾部を破壊した(前二七四)が、しかし彼が新しく気ままにマケドニア王国とギリシア本土に介入すると、開始した攻撃は失敗に終わり、クレオニュマスがスパルタを再建(前二七二)、そしてピュロスはアルゴスにおける夜間の小競り合いで落命した(前二七二)。
真偽はともかく、ピュロスは強健なリ―ダ―であり、臨機の才あり好戦的で、そしてカリスマティックな王であったといわれる。洗練された戦術家であり野戦指揮官であり、それに劣らないだけの戦略家と政治家としての才能を保持し欠けていたのは長期的な将来を見据える展望のみであった。現存する古代の文献を典拠とすれば彼は文人でもあり日記と戦術書をものしたというが、それらのすべては不運にも散逸して、現存していない。

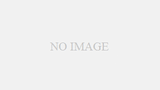
コメント