ナルセス
ナルセス(紀元478年頃 – 紀元573年)は、6世紀のユスティニアヌス帝の高官。宦官であったが、奴隷の身分であったという明確な記録はどこにもない。ペルサルメニア(紀元384年の分割によりペルシアに割り当てられたアルメニアの一部)出身で、両親から東方の宮廷で仕えるための教育を受けた可能性がある。95歳で亡くなったという記述が正しければ、紀元478年頃に生まれたことになる。おそらく幼少期にコンスタンティノープルに連れてこられ、侍従長の地位に就いた。彼は3人の「シャルトゥラリイ」(spectabieles)の1人にまで昇進した。これはある程度の文学的才能を示す地位であり、家内の公文書の保管も含まれる。そのため、おそらく中年期に彼は「praepositus sacri cubiculi」(祭儀の長)となり、プラエトリアニ総督や将軍たちと共に宮廷の最高位に就いた。この立場で、530年には同郷のナルセスとその二人の兄弟、アラティウスとイサクを皇帝の臣下に迎え入れた。かつてペルシアの旗の下で戦っていたペルサルメニアの将軍たちは、ベリサリウスの功績によりユスティニアヌス帝に忠誠を誓い、コンスタンティノープルに赴き、この大宰相から多額の贈り物を受け取った。
532年、ニカと呼ばれる反乱がコンスタンティノープルで勃発し、一時はユスティニアヌス帝の帝位が転覆の危機に瀕した。帝国は、妻テオドラの勇気と、時宜を得たナルセスの浪費によって救われた。ナルセスは首都に忍び込み、かつて皇帝に忠誠を誓っていた「青」派の指導者たちに多額の賄賂を贈り、かつてのように「ユスティニアヌス・アウグステ・トゥ・ヴィンカス(ユスティニアヌス帝に勝利を!)」と叫ばせた。その後、アフリカ戦争とイタリア戦争が勃発した。後者の戦争の4年目(538年)、ベリサリウスの輝かしい勝利は、主君の心に歓喜と恐怖を呼び起こした。イタリアに増援部隊が派遣され、ナルセスがその指揮官に任命された。ベリサリウスは、ナルセスが他の高位の将校と同様に、自分の下で働くことになることを理解しており、ユスティニアヌス帝からこの考えを裏付けると思われる手紙を受け取った。しかし、ナルセスの友人たちは、皇帝の機密に精通した宮廷の重臣であるナルセスがイタリアに派遣されたのは、下級将校としてではなく、独立した指揮権を持ち、自ら軍功を収めるためではないかと、しつこく言い立てた。真相はおそらく両者の中間にあった。ユスティニアヌス帝は、部下の大将軍から最高司令官の地位を剥奪することはできなかったが、常に強力な宮廷特使を傍らに置いておきたいと考えていた。特使の監視は必要だが、妨害は避けたいと考えていた。
二人の将軍は(西暦538年)、アドリア海沿岸のフェルモで会談した。ナルセスがベリサリウスの計画に初めて介入したことは、有益な結果となった。ベリサリウスの下で最高位の将校の一人であったヨハネスは、上官の指示に反してリミニへと進軍し、背後の難攻不落のオジモ(アウクシムム)要塞を占領せずに残していた。彼の大胆な進軍はラヴェンナのゴート族を驚かせ、ローマの包囲を解かせた。しかし、彼自身はリミニに閉じ込められ、飢饉のために降伏を余儀なくされる寸前だった。ベリサリウスとその支持者たちは、彼の無謀さと不服従の罰を彼に払わせる覚悟だった。しかし、彼の友人ナルセスは、リミニの降伏によって帝国軍の評判に打撃を与えることを強く主張し、軍議を自ら持ち出した。そのため、ベリサリウスは、艦隊の動きと併せて山岳地帯を越える華々しい進軍を計画せざるを得なくなり、オジモが陥落する前にリミニを救出した。ベリサリウスとヨハネスが会見したとき、ヨハネスは自分を救ってくれたことをナルセスにだけ、これ見よがしに感謝した。
彼が次に権力を行使した時、あまり幸運なことはなかった。ローマ軍に抵抗していたミラノもまた、飢饉に見舞われていた。交代に派遣された二人の将軍は、行軍中に不名誉なほどに足踏みし、ベリサリウスが更なる増援を要請した際も、新兵の指揮官たちはナルセスからの命令が出るまで動きを拒んだ。ベリサリウスは宦官に手紙を書き、帝国軍の統一の必要性を指摘した。ナルセスは渋々ながらもようやく同意し、必要な命令を出したが、時すでに遅しであった。ミラノは極度の飢餓のために降伏を余儀なくされ、それに伴いリグリア地方全体が敵の手に落ちた。この出来事により、ユスティニアヌス帝は指揮権が部分的にでも分散していることの危険性を痛感し、ナルセスをコンスタンティノープルに召還した。ナルセスがイタリアに戻るまで12年が経過した。その間、ローマ軍とゴート軍の双方にとって、大きな浮き沈みがあった。ベリサリウスの剣によって勝ち取ったかに見えたイタリアは、アレクサンドロスの強奪と失政によって再び失われた。トーティラは新たな軍隊を組織し、ナルセスは5回の困難な遠征(544-548)でベリサリウスを寄せ付けず、今や国土のほぼ全域を掌握していた。しかし、ベリサリウスはこの2回目の遠征では、主君から適切な援軍を受けることはなかった。55年の春、ナルセス2世は大規模で装備の整った軍隊を率いてダルマチア海岸のサロナを出航した。それは名ばかりのローマ軍であった。ランゴバルド人、ヘルリ人、フン族、ゲピダイ族、そしてペルシア人さえもナルセスの旗印に従った。彼らは肉体的な強さと勇敢さにおいてゴート族に匹敵し、受け取った高額な報酬と略奪への期待に鼓舞されていた。
この宦官は軍を率いてアドリア湾奥を回ったようである。艦隊と巧みに協力することで、彼はゴート族の将軍テイアスと戦うことなくヴェネチアの川を渡ることができた。テイアスは彼らの渡河に異議を唱えようとしていた。ラヴェンナで全軍を召集した後、彼は南下した。リミニ前で足止めされることを拒否し、できる限り早く軍勢を縮小させずにゴート王と対峙する決意を固めていた。ゴート族がフルロ峠(ペトラ・ペルトゥサ)を占領していたため、フラミニ街道を通ることはできなかったが、迂回してカーリ近郊の大街道に合流した。少し進んだアペニン山脈の稜線上で、プロコピウス・タギナの招集によりタディーニまで進軍していたトーティラと遭遇した。その後、各将軍による会談、伝言、演説が続いた。ついに戦列が整えられ、おそらく兵力でビザンツ軍に大きく劣勢だったゴート軍は絶望的に敗走した(552年7月)。王は戦場から急いで撤退する際に致命傷を負った。
トーティラの敗北により、イタリア・ゴート王国の最後の希望は失われた。テイアスは後継者と宣言され、ナポリ湾を見下ろす岩だらけのカステラマーレ半島で数ヶ月間、必死の抵抗を続けた。ついに食糧不足に見舞われ平野に逃れ、ポンペイがほぼ見えるサルノ川のほとりで、(553年に)戦いが行われた。この戦いは、見下ろすラクタリウス山(モンテ・レッテレ)の山脈にちなんで一般に名付けられている。しかし、実際の戦いの場所はアングリという小さな町から半マイルほどのところにあり、その記憶は今でもポッツォ・デイ・ゴーティ(ゴート人の井戸)という名で漠然と残っている。この戦いでテイアスは戦死した。彼は東ゴート族最後の王となった。しかしながら、ナルセスの任務はまだ終わっていなかった。ゴート族の招きにより、テウディバルド王の臣下であった好戦的なアラマン人とフランク人7万5千人の軍勢が、二人のアラマン人貴族、ロタールとブッケリン兄弟の指揮の下、アルプス山脈を越えた(553年)。
ナルセスの卓越した戦略的才能は、以前の輝かしい遠征よりも、この遠征においてさらに顕著に発揮された。小規模ながらも勇敢なトーティラとテイアスの部隊に対し、彼は迅速な行軍と、決然とした戦闘への挑戦という方針を採用した。ガリアからの大軍に対処するための彼の戦略は、ファビアン派のそれであった。彼は彼らを可能な限りアペニン山脈の北方に留め、その間にトスカーナの要塞の陥落を完了させた。冬が近づくと、彼は主要都市に軍を集め、野戦での作戦を中止した。その間、アラマン人兄弟はイタリアを進軍し、殺戮と略奪を繰り返した。 554年の春が訪れると、ロタールは軍勢を率いてガリアへ撤退し、そこで略奪した戦利品を安全に保管することを主張した。ペーザロ近郊での取るに足らない戦闘でローマ軍の将軍たちに敗れ、北進を急がされた。ヴェネツィアのチェネダで彼は高熱で亡くなった。彼の軍勢は疫病に見舞われ、疲弊しきっていたため、イタリアでの更なる作戦遂行は不可能となった。一方、兄のブッケリンも、カンパニアのブドウを惜しみなく摂取したことも一因となり、疫病に苦しんでいたため、現在のカプアにあたるカシリヌムに陣を敷いた。しばらくして、ナルセスはここで戦いの申し出を受け入れた(554年)。楔形陣を組んだ蛮族軍は、ローマ軍の中央を突破した。しかし、ナルセスは巧みな戦術で戦列を曲線状にし、両側面の騎馬弓兵がアラマンニクの楔形陣の反対側に陣取る兵士たちの背中に矢を射かけられるようにした。こうして、兵士たちは姿の見えない敵の手によって隊列ごと斃れた。間もなく、行軍が遅れていたローマ軍中央部隊が戦場に到着し、壊滅作戦を完了させた。ブッケリン率いる全軍は壊滅したが、ギリシャの歴史家(アガティアス2世9章)の記述をそのまま信じる必要はないだろう。「蛮族軍3万人のうち、わずか5人しか逃れられず、ローマ軍1万8千人のうちわずか80人しか戦死しなかった」という記述を。ナルセスの他に記録に残る重要な軍事行動は、カプアで彼の指揮下にあったヘルリア王シンドバルを破ったことだけである(しかも、その行動は不明瞭である)。シンドバルはその後反乱を起こし、敗北し、捕虜となり、宦官の命令で絞首刑に処された(565年)。カプアの戦いの13年後(567年)には、ナルセスの重要な軍事行動は終わった。554-567は平和な時代であり、その間、ナルセスはラヴェンナから総督の称号を得てイタリアを統治した。彼はゴート戦争で破壊されたミラノなどの都市を再建した。ローマのサラリア橋には、564年に彼が行った修復の記録が2つ刻まれており、現代まで残っている。
しかし、彼の統治は不評だった。帝政復古の結果、衰弱し熱病に冒されたイタリア国民から最後のソリドゥス(ソリドゥス)を搾り取ることになった。そして、国民は、彼らの寄付金の少なからぬ部分が宦官の私財庫に残っていると信じていた。565年末、ユスティニアヌス帝は崩御し、ローマ人の代表団が後継者ユスティニアヌス2世のもとを訪れ、「ギリシャ人」はゴート人よりも厳しい監督者であり、宦官ナルセスは彼ら全員を奴隷にしようと決意しており、彼が解任されなければ、彼らは蛮族に忠誠を誓うだろうと訴えた。この使節団の派遣は567年にナルセスの召還に繋がり、やや後世の伝承によれば、皇后ソフィアからの侮辱的な伝言も添えられていた。皇后ソフィアはナルセスに金の糸巻き棒を送り、男ではないナルセスに女房の部屋で毛糸を紡げと命じた。「私は彼女のために、一生尽きることのないほどの糸巻きを紡いでやる」とナルセスは言ったと伝えられている。そして直ちに、パンノニアのロンバルディア人に使者を送り、イタリアの産物の一部を携え、このような豊かな産物を生み出す地へ足を踏み入れるよう招いた。こうしてアルボインの侵攻(568年)が起こり、イタリアの大部分が帝国から奪われ、半島の運命は大きく変わった。ギボンがナルセスを「最初の、そして最も有力な総督」と評したことは、形式よりも内容においてより正確である。同時代の著述家は、ナルセスにエクザルフの称号を与えたようには見えない。彼は常に「Praefectus Italiae(イタリア大使)」「Patricius(パトリキウス)」「Dux Italiae(イタリア大公)」と呼ばれているが、皇室における以前の役職名である「Ex-Praepositus [Cubiculi](クビクリ)」または「Chartularius(カルトゥラリウス)」という称号を用いる場合は別である。 この有名な物語は、厳密に同時代の著述家には知られていないようだ。アガティアス(566年から582年の間に著述)、マリウス(532年から596年)、トゥールのグレゴリウス(54年 – 594年)にも、この物語に関する記述は見当たらない。おそらく同時代の著述家による『教皇の書』とセビリアのイシドールス(560年から636年)は、ロンバルディア人への招待について示唆している。 7世紀半ばに執筆したとされるフレデガリウス(いわゆる)と、8世紀末頃に執筆したパウロ助祭は、サガのような詳細を記しているが、語り手が事件から遠ざかるほど、その詳細はより細分化されている。全体として、この出来事は、完全に作り話として片付けるにはあまりにも裏付けがしっかりしているものの、疑いのない歴史的事実の中に位置づけられることはない。
ナポリに隠遁していたナルセスは、教皇(ヨハネス3世)の説得によりローマに戻った。彼は573年頃、そこで亡くなり、鉛の棺に納められた遺体はコンスタンティノープルに運ばれ、埋葬された。彼の死後数年後、彼の莫大な財宝の隠し場所の秘密が、ある老人によってティベリウス2世皇帝に明かされたと言われている。これらの財宝は、貧民や捕虜への皇帝の慈善活動に、絶好の機会を与えたのである。 ナルセスは背が低く、体つきも痩せ型だった。その奔放な性格と人当たりの良さから、兵士たちの間で非常に人気があった。エヴァグリウスは、彼が非常に信心深く、聖母マリアを特に崇拝し、聖母マリアからの合図を思いつくまで決して戦闘に参加しなかったと伝えている。彼の生涯に関する最良の文献としては、同時代のプロコピオスとアガティアスが挙げられる。

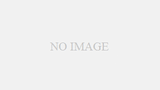
コメント