ヌルハチ、すなわち清の太祖は、西暦1559年(明の嘉靖38年)に生まれ、西暦1626年(明の天啓6年)に没した。ヌルハチは女真族(満州族)の傑出した指導者であり、後金汗国の建国者であると同時に、中国史上において顕著な業績を残した政治家・軍事家である。彼は数十年にわたる努力と奮闘を経て、分散していた女真族の各部族を統一し、女真族の経済力と軍事力を強化し、清朝が関内(中原)に進軍して全国統一を成し遂げるための堅固な基盤を築いた。
ヌルハチは女真族出身で、愛新覚羅を姓とした。女真族は悠久の歴史を持つ民族であり、古来より中国東北部の「白山黒水」の間に広がる広大な地域に居住していた。周・秦時代の粛慎、漢代の挹婁、隋唐・五代の靴鞠は、いずれも女真族の祖先にあたる。12世紀初頭(宋代に相当)、完顔部を中心とする女真族は金朝を建国し、黄河以北の広大な地域を100年以上支配したが、13世紀初頭に元朝に滅ぼされた。東北に残留した女真族の各部族は、明代初期までに建州女真、海西女真、東海(野人)女真の三部族に分かれた。建州女真は幾度かの移動を経て、最終的に蘇子河・渾河流域に定住した。海西女真も南下を繰り返し、その一部が開原辺境の外に移住し、ハダ、イェヘ、ウーラ、フイファに分かれ、扈倫四部と呼ばれた。東海女真は依然として黒竜江中下流域一帯に居住していた。明朝政府は女真族を統治するため「羈縻」政策を実施し、遼東半島に遼東都指揮使司を設置して遼河東西両岸地域を支配。女真族分布地域には多数の衛所を設け、各部族の酋長を指揮使・千戸・百戸などの官職に任命した。建州衛は西暦1403年(永楽元年)に設置され、後に建州左衛・建州右衛が追加され、合わせて建州三衛と呼ばれた。建州女真は明朝後期、自然条件の優位性と漢民族地域への近接性から、漢民族の先進文化や生産技術を積極的に受け入れ、経済・文化の面で比較的発展し、女真族の中で最も先進的な部族となった。しかし当時の明朝政府は腐敗無能で国境防衛が弛み、急速に勢力を拡大した建州女真族の統制を失った。ヌルハチはこうした歴史的環境の中で成長し、その事業を成し遂げたのである。
ヌルハチは女真貴族の出身で、祖父の名はチャオ、父の名はタシ。当初は建州右衛指揮使・王杲の部下であった。万暦初年、王杲が明に反旗を翻し、戦いに敗れて殺害された。ヌルハチの父タシはその後、明政府により建州左衛指揮使に任命された。実母シタラ氏は王杲の娘であったが、若くして亡くなった。継母からの苛烈な扱いを受け、ヌルハチは19歳で家から出て自立した。生計を立てるため、彼は頻繁に撫順に出入りし、漢民族と接触する機会が多く、漢民族の生活を熟知し、漢民族の言語文字を習得した。『三国志演義』『水滸伝』などの作品を読むことを好んだ。こうして漢民族文化はヌルハチの精神生活と軍事政治知識を豊かにし、彼の生活、思想、そして後の統一事業に大きな影響を与えた。
1582年(万暦10年)、明の将軍李成梁はニカン・ウェランを建州三部族の首長に据え、軍を率いて建州女真族で影響力のあるアタイ・チャンキンの古埒寨を攻め落とした。ヌルハチの祖父と父も乱軍に殺害された。ヌルハチは明朝がニカン・ウェランを擁立したことに強い不満を抱いたが、明朝を攻撃する力はなく、父祖殺害の仇討ちを口実に、1583年(万暦11年)5月、父祖が生前に遺した13組の鎧甲を用いて、他の数ヶ所の城寨の首領と連合し、ニカン・ウェランを攻撃した。彼は不意打ちの奇襲作戦で、迅速にトゥルン城と界藩城を陥落させ、ニカン・ウェランはオロジンへ逃亡を余儀なくされた。ヌルハチはこの戦いで、ニカン・ウェランの勢力を殲滅しただけでなく、自らの勢力を拡大することに成功した。
ヌルハチはニカン・ウェランを撃破した後、女真各部族の統一に向けた闘争を開始した。当時の女真社会には氏族社会の痕跡が残っており、人々は基本的に血縁関係で集住し、各部族間で頻繁に紛争が発生し、互いに攻め合った。この現状は女真社会の生産力の発展を阻害していた。したがって、ヌルハチが兵を挙げて統一戦争を遂行したことは、歴史の発展趨勢に合致し、進歩的な意義を持つものであった。1584年(万暦12年)、ヌルハチは軍勢を率いて界藩・サルフ・ドンジャ・バルダの四城連合軍と大戦し、ナシン(マルドゥン寨主)を刀で斬り、バムニ(界藩寨主)を馬上で射殺し、ドンゴ部族を征服した。1585年(万暦13年)、渾河のほとりで、ヌルハチは卓越した指揮能力と勇敢な精神をもって、少数精鋭の兵を率いてトモホ、チャンジャ、バルダ各城の軍勢を大破し、哲陳部を征服した。1586年(万暦14年)から1588年(万暦16年)にかけて、さらに相次いでスクスフ、深河、ワニョンなどの部族を併合し、建州内部の各部族の統一を実現した。
ヌルハチが建州各部族を統一した後、明朝政府は一方では女真の他の部族を支援して彼の統一活動を阻止しようとし、他方ではヌルハチを督佥事に封じて懐柔を図った。ヌルハチはこの微妙な関係を巧みに利用し、表向きは明朝政府に従順を装いながら、密かに自らの勢力を拡大し、統一活動を継続した。1591年(万暦19年)、ヌルハチはさらに長白山南麓の鴨緑江部(ヤルルンガン部)を征服した。彼の絶え間ない拡張は他の諸部族の反発を招いた。1593年(万暦21年)夏、フレン四部(フレン族の四部族)が連合して建州を攻撃したが、これもヌルハチに敗れた。同年秋、葉赫部を中心に、ハダ、ウラ、輝発、ホルチン、シベ、グアルジャ、ジュシェリ、ナインなど九部族が連合し、三万の兵を合わせ三路に分かれて建州へ進攻した。ヌルハチの兵力は相手より少なかったが、彼の勇猛果敢な戦いぶりと高い軍事的才能により、九部連合軍を一挙に撃破し、多くの戦利品を獲得した。さらに勢いに乗じて長白山北麓に進軍し、長白山部に属する建州女真を統一した。
ヌルハチは自らの勢力が絶えず強大になるにつれ、海西・東海女真の統一活動を開始した。1595年(万暦27年)、ヌルハチは武力でハダ部を服従させ、1607年(万暦35年)には輝発部を滅ぼし、1613年(万暦41年)にはウラ部を取り込み、1619年(万暦47年)にはイェフ部(葉赫部)を征服した。海西女真の統一を完了すると同時に、牡丹江、松花江、ウスリー川、黒竜江、綏芬河流域に居住する東海女真の窩集、サハレン、使犬、使鹿諸部など多くの地域も次々に併合した。こうして、1583年(万暦11年)から1619年(万暦47年)までの30年余りの歳月をかけ、ヌルハチはその卓越した先見性と優れた軍事的才能をもって、建州女真・海西女真の全地域と東海女真の大部分を統一し、勢力を拡大して東北地方の割拠基盤を築くと同時に、客観的にも女真社会における経済発展に有利な条件を提供した。女真諸部統一の過程において、ヌルハチは1587年(万暦15年)にフルンハダ山麓にフェイアラ城(現在の遼寧省新賓県家陵公社)を築城し、1603年(万暦31年)にはヘトゥアラ(フェイアラ城から八里)に移り、新都を築いて建国・汗位を称する準備を整えた。1616年(万暦44年)、ヌルハチはヘトゥアラで大汗の位につき、元号を天命とし、国号を大金と定めた。宋代の完顔氏が建国した金と区別するため、歴史上「後金」と称される。
ヌルハチが長期にわたる戦争の中で創設した八旗軍制は、彼が女真各部族を統一し、後に明朝と対峙する軍事的支柱となった。これは女真氏族公社の末期に存在した狩猟組織から発展したものである。女真人の慣習によれば、狩猟に出かける際には十人ごとに一人を首領とし、他の九人を率いて行動した。この十人単位の組織を「牛録」と呼び、その「総領」を牛録厄真(牛録はモンゴル語で「大矢」、厄真は「主」を意味する)とした。ヌルハチは対外戦争と国内鎮圧の必要性に応じ、牛録組織を改編した。1601年(万暦29年)、彼は集めた兵士を三百人ごとに一つの牛録厄真が統括する体制を確立した。その後、部隊が拡大を続ける中、1615年(万暦43年)に正式に八旗制度を確立し、五牛録を一甲喇とし、甲喇厄真(漢訳:参領)が統轄し、五甲喇を一固山(すなわち「旗」)とし、固山厄真(漢訳:都統)が統轄することを定めた。各固山には左右メレ厄真(固山厄真の副官、漢訳では副都統、後の各級厄真は章京と改称)を別途設置した。この時、従来の黄・紅・藍・白に加え、镶黄・镶紅・镶藍・镶白が追加され、八旗が成立した。各旗の兵力は7,500人で、八旗合計6万人。ヌルハチは八旗の最高統帥であった。八旗軍は規律が厳しく、頻繁な訓練により熟練した戦闘技術を有し、ヌルハチが自ら編成した組織的な精鋭部隊であった。
女真内部の統一を達成した後、勢力を拡大したヌルハチは、女真族が明朝の民族抑圧政策に抱く不満を利用し、1618年(万暦46年)に明朝に対して正式に宣戦布告した。同年4月、彼は軍を率いて明領の東州(現在の瀋陽の東南約160キロ)、 馬根丹(赫図阿拉の西南約200里)、撫順の三城と五百余りの砦を攻略した。撤退時には明の広寧(現在の遼寧省北鎮)総兵・張承蔭が率いる一万の追撃部隊を全滅させ、戦馬九千匹、甲冑や武器を大量に鹵獲した。七月、ヌルハチは再び軍を率いて遼東辺境の城壁に侵入し、清河城(現在の遼寧省本渓市東北部)を攻略し、明朝の守備兵一万余人を殲滅した。その後、軍を引いて葉赫を攻撃する準備を整え、明朝の東北支配に深刻な脅威を与えた。
撫順、清河などの城が陥落し、張承蔭ら全軍が壊滅、葉赫から緊急の報告が相次いで北京に届き、明朝廷は震撼した。そこで兵部侍郎の楊鎬を遼東経略に任命し、瀋陽に九万の兵力を集結させた。楊鎬は瀋陽に陣を構え、周到な計画を経て、1619年(万暦47年)2月、四路に分かれた軍勢でヌルハチに対して大規模な攻撃を開始した。第一路は山海関総兵杜松が三万の兵を率い、瀋陽から撫順関を経て渾河南岸に沿って蘇子河谷へ進撃した。第二路は開原総兵馬林が明軍及び葉赫軍1万5千人を率い、開原から東へ三岔口を経て蘇子河流域へ進撃。第三路は遼東総兵李如柏が2万5千人を率い、清河城から南から北へ進み赫図阿拉を攻撃。第四路は遼陽総兵劉缀が本軍と朝鮮援軍各1万人を率い、寛甸から西北へ進軍し、赫図阿拉を攻撃した。これにより戦略上、ヌルハチを包囲する態勢が形成された。しかしヌルハチはこの深刻な状況に慌てることなく、むしろ冷静沈着であった。彼は卓越した指揮術で、兵力を集中し各個撃破する作戦原則を堅持し、三路の明軍を顧みず、まず八旗の全兵力を率いて杜松が率いる明軍主力を迎撃した。三月初一、ヌルハチが軍を率いてサルフ(遼寧省撫順市東、渾河南岸)に接近した時、杜松は既にサルフを占拠し 陣営を構え、自ら一万の兵を率いて河を渡り界藩(現在の遼寧省新賓県西北の鉄背山上屋)を攻撃していた。ヌルハチは即断し、息子であるダイシャンとホンタイジに二旗の兵を率いて界藩へ急行するよう命じ、自ら六旗の優勢な兵力を率いてサルフ山地に駐屯する明軍の大営を猛攻した。八旗兵は塹壕を越え柵を破り、勢いは破竹の如く、一挙に大営を陥落させ明軍を大破した。この時、界藩を攻撃していた杜松軍は山上の後金守備軍とホンタイジの両面から挟撃され、すでに窮地に陥っていたが、まさかヌルハチが主力部隊を率いて参戦するとは予想しておらず、たちまち大混乱に陥り全線が潰走。杜松は戦死し、全軍壊滅した。翌日、ヌルハチは再び八旗の全兵力を集中させ、急行して尚間崖(サルフの北四十里地点)に駐屯する馬林軍を攻撃した。兵鋒が及ぶところ、馬林軍は大敗し、開原へ逃亡した。馬林を撃破した後、ヌルハチはさらに軍を南下させ、敵を深く誘い込む作戦で、アブダリ丘(ヘトゥアラの南東四十里地点)において劉艇軍を全滅させた。三方面での敗報が瀋陽に届くと、楊鐸は慌てふためき、急いで李如柏に撤退を命じたため、李軍は辛うじて壊滅を免れた。この戦いにおいて、明軍は分進合囲の戦術で後金軍を一挙殲滅しようとしたが、ヌルハチの戦略は優勢な兵力を集中させ、明軍が包囲網を閉じる前に、悠然とした動きで各個撃破することにあった。これが歴史に名高いサルフの戦いである。
サルフの戦い後、明軍主力の大半が殲滅され、攻勢から守勢に転じざるを得なくなり、主導権は完全にヌルハチの手に移った。同年6月、ヌルハチは勝利の勢いに乗じて開原を一挙に陥落させ、馬林が戦死。7月には鉄嶺を攻略し、宋招諭成名が戦死。8月には葉赫を滅ぼし、兵鋒は遼沈(遼寧・瀋陽)を直撃した。
明朝政府は遼東の敗局を挽回すべく、楊鎬を逮捕して投獄し、代わりに熊廷弼を遼東経略に任命した。熊廷弼は着任後、東北地方が新たな敗戦により人心離散、士気低下、守備緩慢、戦具不備の状態にあることを認識した。そこで彼は「無謀な戦い」に反対し、守りを主とする方針を堅持。積極的に辺境防衛を整え、城壁を修復し、守備装備を整え、兵士を再召集して民心を安定させた。彼の苦心惨憺の努力により、遼東情勢は安定に向かい、双方は対峙状態となった。しかし、1620年に明の熹宗が即位すると、宦官党の言を聞き入れ、熊廷弼を召還して罷免したため、遼東情勢は再び混乱に陥った。ヌルハチは明政府の混乱を利用し、1621年(天啓元年)春、自ら大軍を率いて水陸両面から進撃し、相次いで瀋陽、遼陽、および遼河以東の大小七十余りの城を陥落させた。年末、ヌルハチは遼陽に遷都し、明進攻の根拠地とした。
明朝が遼東を失った後、熊廷弼を再び遼東経略に任命すると同時に、王化貞を広寧巡撫に任命した。兵権の大半は王化貞の手中にあった。王化貞は軍事を知らず、熊廷弼の固守政策に反対し、十数万の兵力を遼河沿岸に一字に並べて攻勢態勢を取った。ヌルハチは明軍の配置上の弱点を看破し、1622年(天啓2年)に八旗精鋭を率いて遼河を強行渡河、広寧に猛攻を仕掛け明軍を大破した。広寧守備将は城門を開いて降伏し、王化貞は慌てて南へ逃亡した。広寧陥落後、明政府は大学士・孫承宗を薊遼地方の経略使に任命し、袁崇煥は関外に駐屯した。袁崇煥は孫承宗の支援のもと、全力で寧遠城(現在の遼寧省興城)を築城し、関内への要衝を固守した。その後、孫承宗が魏忠賢に排斥され罷免されると、関外の明軍の大半が関内に撤退し、袁崇煥はわずか一万余りの兵で関外の孤城・寧遠を守り抜いた。ヌルハチは明軍の大半が関内に撤退した隙を突き、1626年(天啓6年)正月、13万の大軍を率いて寧遠を包囲した。袁崇煥は堅固な城壁を活かし、防御を厳重に固め、矢石と火砲の威力を最大限に発揮させたため、騎射に長け野戦を得意とする八旗兵はその強みを発揮できなかった。そのため、幾度となく攻城を試みるも陥落させられず、甚大な損害を被った。ヌルハチ自身も砲火で負傷したため、やむなく包囲を解いて撤退した。同年7月、ヌルハチは負傷による重病のため、瀋陽の南40里にある諼鶏健で死去した。享年68歳であった。
ヌルハチは生涯を戦いに捧げた。長期にわたる戦争実践の中で豊富な戦闘経験を蓄積し、その軍事的才能を発揮した。軍務においては規律を重視し、訓練に力を入れ、訓練された勇敢で戦いに長けた八旗精鋭部隊を築き上げ、これが彼の事業全体の重要な支柱となった。戦略上では軽率な戦闘を避け、兵力を消耗させず、自らの戦力を維持することに注意を払った。戦術指揮においては、智謀を巧みに用い、優勢兵力を集中させて敵の弱点を攻撃することを堅持し、数で劣るながらも勝利を収めた数々の戦例を生み出した。ヌルハチは清朝政権の礎を築いた人物であるだけでなく、中国歴史上傑出した軍事家でもある。

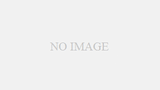
コメント