曹操
曹操は中国歴史上非常に影響力のある人物であり、天才的な軍事家であると同時に偉大な政治家・文学者でもあった。彼の名はまさに家喻戸曉、老若男女を問わず広く知られている。
曹操は西暦155年(後漢・桓帝永寿元年)、沛国譙県(現在の安徽省亳県)に生まれた。字は孟徳、幼名は阿瞒。漢の相国・曹参の子孫である。祖父の曹騰は宦官で、中常侍・大長秋(宦官の長官)を務め、桓帝の時代に持費亭侯の爵位を得た。父曹嵩は曹騰の養子で、太尉の地位まで昇進した。曹操が生きた時代はまさに東漢末期の大動乱期であり、封建的な軍閥が絶え間なく争い、豪族や世族が領地を割って勢力を張り、国家全体が四分五裂し、東漢王朝は統治基盤が崩れ、崩壊寸前だった。中国史上で有名な黄巾の乱(農民大蜂起)もこの時期に勃発した。後漢王朝はあらゆる手段を動員して農民の反乱を鎮圧し、曹操も支配階級を代表する軍事家・政治家としてこの罪深い活動に参加した。しかし曹操は生涯を通じて、主に豪族の割拠を討伐し、軍閥混戦を終わらせ、中国全土を統一する活動に力を注いだ。中原地域の封建経済を守り発展させ、社会秩序の安定を促進したことで、後の西晋による全国統一の基礎を築いたのである。長きにわたり、封建支配者たちは曹操を恣意的に攻撃し、その本来の姿を変質させてきた。魯迅はかつて指摘している。「曹操について語る時、我々は容易に『三国志演義』を連想し、さらに舞台上の白塗りの奸臣を思い浮かべるが、これは曹操を観察する真の方法ではない」 「実際、曹操は非常に有能な人物であり、少なくとも英雄であった」。したがって、歴史的唯物論の観点から事実に基づいて曹操の一生を分析してこそ、彼を全面的かつ正しく認識・理解し、その歴史的本質を明らかにすることができるのである。
曹操は青年期、官界に入った当初から豪族を恐れず、自らの主張を貫き実行する勇気を持っていた。西暦174年(後漢・霊帝熹平3年)、曹操が20歳になったばかりの時、人々に推挙されて洛陽の北部尉(治安維持の地方官で県令より一つ下の職位)に就任した。豪強に反対し、後漢王朝の法制度を守るため、赴任するとすぐに尉衙門の左右に十数本の五色棒を懸け、禁令に違反した者は一律に棒で打ち殺した。自ら率先して行動し、漢の霊帝が寵愛した宦官・蹇碩の叔父を五花棒で打ち殺したこともあり、一時的に洛陽の豪強や権貴を震撼させ、誰も禁令に違反しようとはしなくなった。官位は低く職責も軽微であったが、彼は直接霊帝に上書し、朝廷を掌握する「三公」(太尉・司徒・司空を指す)を弾劾し、彼らが豪族や権貴を庇護する数々の罪状を暴露した。しかしこの時、後漢王朝はすでに腐敗の極みに達しており、皇帝は豪族や権力者の傀儡に過ぎなかった。彼の上書は全く役に立たなかったばかりか、世族や豪族勢力からの反感を買う結果となった。当時の状況下で中国を統一し、割拠勢力を排除するためには、強力な軍事力を掌握し、戦争によって問題を解決するしかなかった。
曹操の最初の軍事活動は、黄巾の乱の農民軍鎮圧に参加したことに始まる。185年、曹操は済南相に昇進し、「政治と教化を良くして名声を確立する」という志を抱き、各県の悪行が甚だしい長吏をすべて罷免し、淫祀を禁じ、邪悪な鬼神を排除した。彼は廟や祠堂を全て取り壊し、こうした祭祀を禁止する命令を下したため、当時「世の淫祀はこれにより絶えた」と言われるほどであった。しかし地方の世族である藁強や申英といった権臣たちの反対に遭い、曹操は間もなく職を辞して帰郷した。189年、董卓が乱を起こし洛陽を攻め、皇帝を廃立し人民を殺戮したため、各地の世族・豪強が次々と台頭し、兵を擁して自立した。同年12月、曹操は陳留に到着し義兵を募った。彼は兖州にあった曹家の財産を軍資金として分配し、曹氏の宗族の子弟や部曲を中心に、迅速に5千人以上の部隊を組織した。190年正月、関東の各州郡が相次いで兵を挙げ、董卓討伐の連合軍を結成した。当時、連合軍の統帥・袁紹が臆病に後退したため、曹操は厳しく非難し、自ら部下の将兵を率いて成皋へ進軍した。董卓の大将・徐栄と一日中激戦を繰り広げたが、兵力が少なく援軍もなかったため、大敗を喫した。しかし彼は落胆せず、引き続き兵を募り、自らの力で袁紹を筆頭とする分裂割拠勢力を滅ぼす決意を固めた。191年と192年、曹操は兗州を掌握し軍事拠点を築くとともに、青州軍30万人余りを再編し強大な軍事力を発展させた。この時点で曹操は中原を争い群雄を撃破する主導権を握っていた。まず袁術と公孫瓒の連合攻撃を撃退し、続いて徐州を割拠する陶謙を二度征伐して兗州における支配基盤を固めた。兗州治中従事の毛責は曹操に「天子を奉じて臣従しない者を制し、耕作を修め軍需物資を蓄える」ことを進言した。曹操はこの提案を採用し、豪強の割拠勢力を滅ぼすための政治的・経済的方針とした。この正しい方針を実現するため、196年、曹操は漢献帝を洛陽から連れ出し、許昌に迎えて都とし、国号を建安と改め、「名分を整えて」豪強割拠勢力との闘争を開始した。楊奉、張繡、劉表など中原を割拠する封建軍閥を次々と打ち破り、中央政権における自身の地位をさらに固めた。続いて、最大の豪強割拠勢力を打倒し、中国北部を統一する決定的な戦役が始まった。
この戦いは、わが国の戦争史に名高い官渡の戦いである。曹操が中原を争っていた頃、「四世三公」の豪族・袁紹は北方で勢力を拡大し、割拠を拡大していた。西暦197年、曹操は情勢に迫られ、やむなく大将軍の地位を袁紹に譲った。袁紹はすでにその勢力を冀州、幽州、青州、并州の四州にまで拡大していた。袁紹は自らの広大な領土と強大な兵力を背景に、出身が卑賤でかつて地位の低かった曹操をずっと見下し、曹操を打ち倒して兗州を奪おうと企んでいた。曹操は袁紹の本性を深く理解しており、早々に準備を整えていた。官渡の決戦は200年に起こったが、実は197年に曹操は特別会議を開き、袁紹打倒の戦略を研究。謀士・郭嘉や荀彧らの意見に基づき、北征で袁紹を攻撃し、西方の馬騰・韓遂らと連合して二正面作戦を回避する方針を決定していた。198年秋、曹操は呂布を平定し徐州を奪取、袁紹討伐の前哨戦を開始した。199年3月、呂布を滅ぼした曹操は軍を率いて黄河に臨み、張楊を破り河内を収め、袁紹打撃の重要な戦略的配置を完成させた。これにより曹操軍と袁紹軍は直接対峙し、決戦は避けられない状況となった。当時の両軍の情勢は袁強曹弱であり、袁紹は精鋭十万、戦馬一万匹を選抜し、河北前線の黎陽に集中させ、黄河を渡って南進し許都を直撃する準備を整えていた。一方、曹操が集中させた兵力は三、四万人に及び、自ら率いて官渡(現在の河南省中牟県北東)を守り、袁紹と川を隔てて対峙した。大戦の序幕は白馬・延津で幕を開けた。傲慢な袁紹は曹操の「東を声にして西を撃つ」策略に嵌り、大将・顔良を失った。さらに軍が軽率に南渡したため曹操の伏兵に遭い、大将・文醜が斬られた。曹操は自ら指揮を執り、少数で多数に抗して大勝を収め、士気を大いに高め、官渡決戦の勝利の基礎を築いた。200年4月(漢献帝建安5年)、曹操は官渡を堅守した。この時点での基本的な軍事情勢は、依然として袁紹軍が兵力・兵糧ともに優位で、曹操軍は兵力・兵糧ともに劣勢であった。強敵を前に、曹操は一方では深い堀と高い塁を築いて陣地を固守し、有利な機会を待った。他方では軍紀を厳しくし、法治をもって軍を統べ、内通者を鎮圧して内部を固め、戦闘力を強化した。袁紹は直前の敗北の教訓を顧みず、傲慢で横暴な態度を改めず、謀士たちが「曹操と正面から戦わず、迂回して許都へ進み漢帝を人質に取る」と進言したにもかかわらず、誤って正面から曹軍を攻撃する方針に固執した。曹操は長期にわたり陣を堅守する中で、袁紹軍は兵力は多いものの消耗が大きく、後方の補給が途絶え、糧草の供給・輸送が深刻な問題となっていることを把握していた。曹操は謀士たちと対策を慎重に検討し、「軽装兵で奇襲し、不意を突いて蓄積した物資を焼き払え」という意見を採用。二度にわたり袁紹の軍糧・軍草を襲撃・焼却した。特に二度目の攻撃では、袁軍の物資を焼き払っただけでなく、袁紹の後方基地である烏巣をも破壊した。この時、袁紹軍の士気は大きく乱れ、曹操は勢いに乗じて自ら全軍を率いて総攻撃を仕掛けた。袁軍は敗走し、袁紹はわずか八百名の親衛隊を率いて黄河以北へ逃れたが、主力は全滅し、以後完全に衰退した。202年5月、官渡での大敗に鬱憤を募らせた袁紹はついに吐血して死亡した。これは少数で多数を打ち破り、弱者が強者を制した有名な戦役である。官渡の戦いの結果、黄河南北の豪族による割拠勢力は打倒または弱体化され、中国北部には統一され比較的安定した局面が訪れた。
北方の統一計画を最終的に完成させ、さらに南進して全国統一を実現するため、曹操は203年から207年にかけて、世家豪強の残存勢力を繰り返し掃討した。203年と204年、曹操は相次いで袁紹を破り、袁譚を斬り、鄴城の袁氏割拠勢力の拠点に直撃し、正式に河北に足場を築くことができた。続いて北上し、袁氏グループと以前から結託していた「三郡烏丸」(遼西・遼東・右北平の三郡にまたがる遊牧部族の統治集団の総称)を攻撃した。進軍途中、田畴と郭嘉の助言を受け入れ、輜重を置き去りにして軽装で迂回。龍寨から白檀の険しい山路(現在の河北省承徳県西)を越え、烏丸軍を不意打ちし、一戦で撃破した。「死者は野に横たわる」ほどの惨敗だった。207年9月、曹操は勝利を収めて帰還し、渤海の海岸を行軍しながら「東に碣石に臨み、滄海を観る」と詠み、「秋風蕭瑟、洪波湧起」という 「老いた駿馬は伏せて揚げる、志は千里にあり。烈士は暮年、壮心は止まらず」という雄壮な詩篇で、中国統一の大志を語った。すでに「老いた駿馬」となってもなお、「千里」を駆ける意志を示したのである。
「山は高くても厭わず、深きを厭わず。周公は吐き出した食物を再び口に運んで客をもてなした。それゆえ天下の心が帰順した」。統一の大志を抱く曹操は、南北が依然分裂状態にある現状に満足するはずがなかった。208年正月、自丸から戻ったばかりの彼は、南北の要衝である荊州を攻める準備を始めた。当時の荊州は現在の河南省、湖北省、湖南省、貴州省の一部を管轄しており、荊州を領していた劉表は漢王朝の同族であり、南方の主要な割拠勢力であった。荊州を奪取して初めて長江を越えて南進し、南北統一を実現できるのだ。同年7月、曹操は自ら大軍を率いて南下し、圧倒的な兵力で劉表と連合して曹操に対抗した劉備を打ち破った。当時劉備は文では諸葛亮、武では関羽・張飛・趙雲ら名将に支えられていたが、兵力が弱く劣勢に追い込まれ、わずか数十人で逃れるのがやっとであった。曹操は劉表の側近を排除した後、迅速に南下して江陵を占領し、荊州の一部地域を掌握した。続いて彼は長江を下って劉備を追撃し、巴丘まで進軍した。これにより江南に雄踞する孫権グループと直接対峙し、新たな大戦争――赤壁の戦いの序幕が開かれたのである。
曹操が南下して孫権を攻撃することについては、準備を整えていたと言える。優勢な兵力を集結させ、名目上は八十万、実際には二十数万の兵力を擁し、専用の玄武池を掘削して将兵の水上戦闘訓練を行った。しかし、ここ数年連戦連勝し、攻めれば必ず落とすという状況が続いたため、曹操は慢心し、客観的な情勢を正しく分析できなくなっていた。当時、北方は統一されていたものの、その基盤は決して固くはなく、馬超と韓遂という二つの強力な割拠勢力が依然として曹操の後方を脅かしていた。主力部隊は連年の征戦により「烏丸三郡」を平定した後、遠征から戻ったばかりで休養も取れていなかった。北方の将兵は陸上戦を得意としており、水戦は初歩的な訓練を受けたものの、まだ不慣れであった。また厳冬期であり、戦馬の飼料が不足し、将兵は南方の気候に適応できていなかった。曹操が江陵から孫権征伐に出発した際、ある者が進言した:勝利の成果を固め、生産を発展させ、民を安撫し、軍威を壮大にして、平和的に江東地方を統一すべきだと。しかし曹操は全く聞き入れず、孫権を軽視し、新たに敗れた劉備など言うまでもなかった。自らの力を過大評価し、必ず孫・劉両軍を打ち潰せると考えていた。孫権と劉備の兵力は少なかった(孫権はわずか三万、劉備は一万余りしか動員できなかった)が、休養十分で待ち構え、現地事情に精通し、水戦に慣れ、南方の気候に適応していた。さらに諸葛亮と周瑜の天才的な軍事指揮が加わり、少数で多数を打ち破る客観的条件を備えていた。この時、曹操は北方の将兵が水上生活に不慣れな弱点を克服するため、船を鎖で繋ぎ合わせた「連環船」を考案した。船上での移動には便利だったが、戦船同士が互いに拘束され機動性が失われるという戦術上の重大な誤りを犯したのである。孫権と劉備は曹操の思想的油断と戦術的誤りを利用し、偽りの降伏を装って戦船に火を放った。曹操の兵士は焼死や溺死が多く、孫劉連合軍は猛烈な追撃を加えた。曹軍は大敗し、甚大な損害を被り、曹操は残存部隊を率いて譙郡へ撤退せざるを得なかった。曹操の赤壁の戦いの敗北は、一方で孫権の江東における地位を固め、中原と江南の対峙局面を形成した。他方で劉備に休養と再起の機会を与え、南下して荊州を攻め、勢力を拡大し、ついに益州を獲得することを可能にした。これらは後の魏・蜀・呉の三国鼎立の前提条件を創り出したのである。
赤壁の戦いの敗北により、曹操は南方統一と全国統一を実現するには、まず後顧の憂いを断ち、堅固な後方を確立しなければならないことを痛感した。一時期の休養を経て、西暦211年、曹操は残存する割拠勢力の討伐を開始し、215年までに馬超、韓遂、宋建、張魯らを次々と平定し、ついに北方の統一を完全に実現した。「領土を三千里に拡大し、往還は飛ぶが如く速やか。歌と踊りを伴い鄴城に入り、望むところを得ずして違うものなし」という境地に至ったのである。
曹操が軍事的に割拠勢力を殲滅し北方統一を達成できた要因の一つは、生産発展に有利な屯田制(屯田農家が官牛で耕作した場合、収穫の60%を納め、自牛使用時は50%納付。兵役・労役を免除され、専ら農桑業に従事)を堅持した点にある。彼は屯田制の実施による生産発展、兵力の強化と食糧の充足こそが戦争勝利の鍵と確信していた。屯田の管理強化のため、中央から地方まで専任官吏を設置した。朝廷には「典屯田事」を置き、各州郡には典農中郎将・典農都尉を配置し、屯田事務を専門に管理させた。さらに各地の官吏に対し、水利事業を大いに興し、屯田を整備するよう命じた。屯田制実施後、多くの流離した農民が土地に戻り、北方の農業生産は回復・発展を遂げた。「民は農を勤め、家々豊かに実り、倉は溢れんばかりに満ちた」。屯田の実施により各地で食糧が充足し、軍隊は現地で補給を受けられ、長距離輸送の必要がなくなり、統一戦争を力強く支援した。
曹操が北方統一戦争で次々と勝利を収めた背景には、彼が「人材は唯賢を以て用いる」という正しい方針を貫いたこともあった。彼はたびたび求賢の勅令を下し、「今、天下はまだ定まっておらず、まさに賢者を求める急務の時である」と指摘した。「諸君よ、我を補佐し、才能ある者を顕彰せよ。唯才を挙げて、我が用いるべし」。彼は「治国用兵の術」を持つ者であれば、たとえ「行いが悪く、汚名を着せられ、笑われるような行い」をしていても、その能力を尽くして選び用いるべきであり、「何一つ見逃すな」と考えていた。そのため、多くの出身は卑賤ながら真の才学を持つ人々が彼の周りに集まった。文官では荀彧、郭嘉、荀攸、満寵ら、武将では張遼、徐晃、龐徳、于禁ら、いずれも豪族の出身ではなく、才学と能力があったからこそ曹操に抜擢され重用されたのである。才能ある者に対しては、たとえかつて自分に反対した者であっても、改心したならば曹操は差別せず重用した。彼は人材を賞罰分明に扱い、功績ある者は必ず褒賞し、過ちある者は必ず罰した。部下との付き合いにおいては、威張ることなく、細かいことにこだわらなかった。
曹操は軍を法治で統治し、国を法治で治めることを堅持したため、軍紀は厳明で国家は安定し、統一戦争の勝利を保証した。曹操は自ら多くの軍官兵が遵守すべき条令を公布し、上下の統一と厳格な執行を求めた。かつて軍行進中に馬が農民の麦畑を踏み荒らした者を処刑するよう命じたため、騎兵は麦畑を通る際必ず馬から降りて麦を支えながら進んだ。ある時、行軍中に乗っていた馬が驚いて跳ね、自ら麦畑に飛び込んだことがあった。彼は主簿に罪を問うよう求めたが、主簿は「春秋の道理によれば、統帥が自ら罪を問うことはできない」と答えた。曹操は「法を定めた者が自ら違反すれば、部下を統率できない。私は統帥として自殺はできないが、それでも刑を加えねばならない」と述べた。彼は剣を抜いて髪を切り落とし、その罪を身をもって償った。全軍は畏敬の念を抱き、二度と違反する者はいなかった。豪強を断固として打倒し改革を実施するため、曹操は『抑兼併令』を制定・公布し、「国や家を持つ者は、少ないことを憂うより不均等なことを憂い、貧しいことを憂うより不安定なことを憂うべきである」と指摘した。」と記した。豪族や名門による不法な併合を禁止し、今後一畝あたり田租四升、各戸絹二匹・綿二斤を納めることを定め、その他の項目を勝手に増発することを禁じた。豪強が「弱民」に租税を肩代わりさせる隠蔽行為も許さなかった。曹操はさらに役人を各地に派遣して法令執行を監督させ、違反者には家財没収・斬首・強制労働といった厳しい処罰を科した。
曹操は生涯、豪強の割拠勢力を掃討し中国を統一する事業に没頭し、揺るぎなく、磊落として光明であった。豪強割拠勢力を打倒する過程で、多くの反対に遭い、長期にわたり軍政の大権を掌握し「不遜の志」を持つと攻撃された。しかし彼は当時「江湖未静(天下はまだ平定されていない)」と冷静に認識し、「慕虚名(虚名を求めること)」のために権力を放棄すれば「災禍を招き、子孫にまで及び、国家が傾く」と悟っていた。しかし、当時の漢皇室から与えられた「封邑」については、固く辞退した。統一事業に有利であり、豪族に口実を与えないため、彼は断固として皇帝を称せず、過度の封賞も拒んだ。彼の部下は何度も皇帝即位を勧めたし、孫権も書簡で即位を要請した。彼はいずれも厳しく拒否した。さらに彼は、孫権のこの行為は自分を「炉火の上で焼く」ように仕向け、より多くの人々に反発させる意図があると指摘した。
曹操の一生、特に彼の軍事活動は、当時の豪族による割拠という後退した状況を打開し、国家統一と社会発展を促進する上で、進歩的な役割を果たした。彼は自ら『孫子兵法』を編纂し、序文を記した。序文から判断すると、彼は「略解」(注釈)も作成したが、残念ながら現存していない。彼自身は体系的な専門軍事著作を残していない(『孟徳新書』を著したとの伝承があるが、史書には見られない)が、軍事に関する「令」「教」「襲」「書」などの文書を数多く遺している。もちろん、彼の詩賦などの著作は文学史において非常に顕著な地位を占め、「一代の風潮を開いた」ものである。西暦220年正月(漢献帝建安25年)、曹操は関羽を南征した帰途に病に倒れ、洛陽で死去した。彼は遺命として、子息や配下の百官に対し、死後も未完の事業を継続するよう命じた。葬儀は必ず質素に執り行い、「服は質素なままに弔う」こと、そして「金玉や宝石を蔵するな」と遺した。

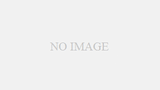
コメント