☆出典情報☆
原著:Byzantium the Imperial Centuries A. D. 610-1071/Romilly Jenkins1966
☆免責事項☆
本翻訳は、原著者Romilly Jenkins氏の論文を日本語に翻訳、要約したものであり、内容は原著者個人の見解に基づいています。
☆訳者の立場☆
本翻訳は非営利・教育目的で公開されており、翻訳者は原著の内容を忠実に反映するよう努めています。
◇ヘラクリウス帝◇
565年、ユスティニアヌス大帝が崩じます。ベリサリウスやナルセスと言った名将を駆使してローマ帝国の再建を目指したユスティニアヌスですが、現実にはそんなことは不可能でした。そもそも帝国が東西に分裂したのはそうしなければ自身を養えない状態にあったからで、そんな東西帝国を無理矢理ひとつに合わせようとしてもうまくいくはずがありません。ユスティニアヌスは自分が誤ったことを認めず、またおそらく気づきもしなかったのでしょうが、彼の政策に対する社会情勢不安は日増しに大きくなりました。
しかしユスティニアヌスが倒れた後、予想されたような大崩壊が訪れることはありませんでした。むしろ東方やドナウ方面では事態改善の兆しすらあったといいますが、まあやっぱり不平不満は蔓延していました。とくにひどかったのはエジプトとシリアだて、宗教紛争の激しさはかつてないものになったといいます。さらに、ユスティニアヌスの浪費によって国庫は空になっていました。人的資源と兵士も慢性的に欠乏していました。
本稿の主役はローマ帝国の再建者ヘラクレイオスですが、彼の前に帝位に就いた二人の皇帝、ティベリウス2世とマウリキオスはそれぞれかなりに優れた人物でした。とくにマウリキオスはヘラクレイオスが完成させることになる軍事州制度――テマ制――の、実質的創始者と言っても良い人物でした。まあ、そのシステムを発展改良して完成させたのはもちろんヘラクレイオスなわけですが。
マウリキオスは帝国の再生を標榜し、その非凡な軍事的・政治的才能を傾注しました。帝国の生命線はイタリア半島やスペインではなく、今や小アジアのアナトリアに移っていました。人的資源(最優秀の戦士)・農業物資(豊かな穀倉地帯)・鉱物資源(金に代表される貴金属)のすべてを、ビザンツ帝国はアナトリアに負っていたのです。そしてアナトリアは同じだけ豊かなアルメニアにつながる回廊の鍵を成す土地でもありました。
ユスティニアヌスを破滅させた原因の最大なものは、まちがいなくペルシアとの戦争でした。ホスロー2世とベリサリウスのペルシア戦争はベリサリウスをもってしても完勝とはいかず、戦後、どちらが購い金を支払ったかと言えばローマの側なので実質的にはローマの負けといってもよかったと思います。
マウリキオスはユスティニアヌスからペルシア戦役を継承しましたが、財産と兵士は前述のように限りなくゼロに近かったわけです。わずか4000名の近衛兵を招集することすら困難でした。それでも彼が10年間帝位を保ちえたのは将軍フィリッピコスと、そして本稿の主役ヘラクレイオスの父である老ヘラクレイオス、この二人の勇気と才覚に寄りました。戦功によりヘラクレイオスはカルタゴ総督府の総督に任ぜられ、そしてマウリキオスは軍事力でなく政治力でペルシアのホスロー3世を制しました。反乱がおきてローマに亡命してきたホスローを受け入れたマウリキオスはたぐいまれな政治手腕によって彼をペルシアの王位に復させたのです。
これによってマウリキオスは東方の脅威に注力できるようになりました。ただし、アヴァール人をはじめとするドナウ川流域の驚異は容易な相手ではありませんでした。バルカン半島で甚大な損害を被ったローマ軍は602年、現地の物資で生活拗ねよう命じた(命じざるを得なかった)マウリキオスに反乱を起こし、将軍フォカスを総督に選出します。マウリキオスの任期は倹約と吝嗇により徹底的に失墜していました。本来なら名君と称えられるべき彼は、受けるべきではない不当な評価を帝国中から受けていました。
フォカスは帝都に直行するとマウリキオスと4人の息子を虐殺しました。602年11月26日の事です。都市民兵も誰ひとりとして皇帝一家を救わなかったといいます。
フォカスが帝位につくとペルシアのホスロー3世が「マウリキオスを討つ」として挙兵、これに抗いうるローマ将軍は今や一人もいません。フォカスは人事不省でうずくまり、なにひとつなすところがありませんでした。民衆は救いはどこから来るのかと希求しました。
救いはアフリカからやってきました。老ヘラクリレイオスの息子ヘラクリレイオスが、いとこのラケタスとともに名を受けて出撃しました。艦隊をヘラクリレイオスが、陸軍をニケタスが率い、先に帝都に入ったものが皇帝になるとの約束が交わされていました。610年10月4日、ヘラクレイオスはフォカスをとらえ、「お前の玉座はこれか?」と聞きました。「お前が私よりうまく統治できるとでも?」と答えたフォカスはたちどころに切り刻まれ、死体は「牛の広場(フォロム・デ・オクス)」で燃やされることになります。
かくして帝位についたヘラクリウスはローマ史上もっとも傑出した際角の持ち主でした。ヘラクレイオスは恐らくアルメニア系であり、それは非常に大きな意味を持っていました。これ以降、ビザンツの偉大な支配者のほとんどはこの血統に属すからです。
610年にヘラクレイオスが最高権力を掌握しても、国内の情勢は即座に改善するというわけにはいきません。むしろ暴君フォカスの9年続いた統治で事態は悪化していたので、ヘラクリウスの治世の始めは失敗と敗北の連続でした。ペルシアの新軍の前に敗北し、613年にはキリキアが、614年にはエルサレムが奪われました。総主教ザカリアスは捕虜になり、キリスト教世界の至宝である聖十字架はペルシアの首都に持ち去られました。615年ペルシア軍は再びハルケドンに迫り、同年、スラヴ人がギリシア半島を占領します。617年、ペルシアはエジプト遠征を開始しました。アレクサンドリアが陥落し、エジプトの穀倉地帯は永久に閉ざされました。
618年、ヘラクレイオスはコンスタンティノープルを離れる決断をします。エジプトへの反攻のためにはカルタゴへの撤退が最善であるとの判断でしたが、ここで市民は騒然となりました。必死で見捨てられることを拒み、総主教セルギウスも「都の女王を見捨て給うな」と懇願して皇帝に都を見捨てないと誓約するよう説得します。
ヘラクレイオスはにとってここが唯一最大の好機でした。この機会を捉えたことで、この瞬間に皇帝と民衆の間の契約が更新されました。皇帝が望むすべてのものを、民衆は躊躇なく提供することを約束しました。協会は莫大な財宝を金貨に買えて皇帝の軍費に献じました。この後、きびしいざいせいきんしゅくがじっこうされましたが、不満の声は微塵も上がらなかったと言います。ビザンツは新軍を編成し、それをヘラクレイオス自身が率いました。
テマ
ヘラクレイオスはマウリキオスの創案した軍事州制――テマーーを発展させました。実のところ彼がテマの創始に関連したという説から無関係であったという説まで、あらゆる見解が存在しますが、本稿ではヘラクリウスがテマ制を完成させた人物であるとして話を進めます。
ある説によれば、ヘラクリウスは622年ペルシア遠征をはじめる前に、アルメニア州とアナトリア州(当時の小アジア東部および中部の大部分を占めていた)にテマを創設したと言います。彼はこれを2~3世紀後に機能した軍隊とほぼ同様に設計し、運用したとあり、その内容は戒厳令にもとづく統治、権限の分散化、自由農民層における兵士の荘園制でした。また、家長が兵役を務め、家族が農耕に従事することもここに定められました。この改革によりヘラクレイオスは軍隊の強化と農業生産の増産を達成し、農村を活性化することで中央財政を救済しました。これについて否定的な意見もありますが、テオファネスが627年に関する記述として「アルメニアコイのトゥルマルヒ」に言及しており、トゥルマというのはテマの細分単位の名称で西ローマにおけるエグザルカート(副王領)の細分単位が「公国(duchy)」であったのと同義ですので、少なくともヘラクレイオスの時代にテマという制度が存在したのはまず、肯定するのに問題はないかと思います。カルタゴ出身のヘラクレイオスは総督府の組織を熟知しており、これらの改革を意識的かつ成功裏に小アジアへと移入したのだと言われます。
ヘラクレイオスはその後6年間、ペルシアとの戦いに明け暮れました。明確な目的意識のもと、ペルシア帝国打倒に専念し、ほかのことは一切顧みず、バルカン地方の属州を放棄し、西方の難局もほぼ歩すれ去られたと。後方での剣聖工作も無視したヘラクレイオスは626年ペルシアがアヴァール人と結んでコンスタンティノープルを襲撃するという恐るべき計画すらも無視しました。ただし皇帝の在不在にかかわらず、彼は同胞たちに偉業を達成させるだけの霊感を与えていた感があります。
626年8月7日木曜日の夜、金角湾でスラヴ艦隊を壊滅させた戦い――ビザンツ史上最も輝かしく記憶に残る武勲の一つ――は、少なくとも間接的にヘラクレイオスの功績でした。彼の東方遠征の詳細についてわかっていることはそう多くありませんが、彼は常に彼を裏切らなかった新軍を率い、困難な地形において、不利な状況下において、しばしば驚くべき勝利を収めました。
627年後半、決定的な戦いがニネヴェ近郊で繰り広げられました。皇帝は茶褐色の軍馬ドルコンに跨り、自らの手で3人の将軍を斬り倒したと言います。ペルシアの将軍ラザタスが戦死し、ペルシア軍は壊滅、皇帝の連戦連勝がついにペルシア軍を挫いた瞬間でした。この敗北を受け、ペルシアでは内乱が発生。ホスロー5世は実の息子に殺され、628年に和平が成立。クシテフォンで聖十字架が奪還され、エルサレムへと返還されました。皇帝は「主の名において喜びなさい」で始まる布告文とともに凱旋を宣言し、この布告文は聖ソフィア大聖堂の説教壇で朗読されました。
ヘラクレイオスの再建したローマ帝国は、歴史的観点からいって真のビザンツ帝国でした。ここでその重要な特徴を挙げるなら、キリスト教とヘレニズム文化です。後者ギリシアの叡智は、教養あるローマ人ならだれもが習得を誇りとしたものでした。何千人もの書記官や官僚にとって、ギリシア語の知識は生計の源でした。そしてヘラクレイオスによってギリシア語は帝国公用語となったのです。皇帝は「バシレウス」と呼ばれることになり、この称号はこれ以後、帝国の支配者にのみ許されて外国の君主と共有されることは(最も厳しい外圧にさらされた時をのぞいて)決してありませんでした。それまで、ビザンツ文学自体には文学的価値がほとんどありませんでしたが、これ以降、何百もの非ギリシア系民族からなる住民に帝国は共通のギリシア語とその文化という遺産を与えたのでした。もっとも、眉山の角民がギリシアの教養をものにするためにはこれから数百年を要し、この時点におけるビザンツ人は単に「ギリシア語を話すローマ人」でしかありませんでしたが。
キリスト教という意味では「キリストに選ばれた正統な民」への帰属意識は、中世において帝国の統一を実現させた要素の……おそらくは最も強い……ひとつであり、それはもちろん教養階級に限定されたものではありませんでした。とはいえキリスト教は何世紀にもわたり、分裂の根本原因、あるいは口実として機能してきました。
キリスト教異端のなかでもっとも強力かつ驚異的なものはえうてぃケスの異端でした。彼の主張は救い主が単一の神聖のみを有していたというもので、ゆえにこの異端は「単性論」と呼ばれます。これに対し、451年のカルケドン公会議で定式化された正統派的見解は、救い主が神性だけでなく完全な人性を備え、近藤も変化も分裂も分離もなく、ふたつの本性において同一のキリストであり、各本性が一つの位格と一つの実態に一致する、というものでした。
この正統と異端の論争はゼノやユスティニアヌスたち専制君主ですら鎮めることができませんでした。キリストの花嫁である教会の分裂を癒す公式声明も勅令も、決して考案されませんでした。最後の試みはサラセン人の大災害のまさにその時、ヘラクリウスによってなされました。長い思索の末、639年にヘラクリウスはシリアの異端者たちに、救い主は、その本性の数や状態がどうであれ、単一のエネルギーと単一の意志によって生かされていたと提案しました。一瞬、この解決策が皇帝や教会人たちが長年求めてきた万能薬となるかもしれないと思われました。単性論者たちはこれを認め、教皇ホノリウスさえも非難しませんでしたが、しかしこれは単なる応急処置に過ぎませんでした。新たな解決策はヘラクレイオスによって「エクテシス(説明書)」として知られる文書で承認されましたが、これも正統派によって拒否されました。いずれにせよ、解決は遅すぎました。639年までにサラセン人はシリアの支配者となり、エジプトへと進軍していきていたのです。
ヘラクレイオスがホスローに対する最初の遠征に乗り出したまさにその瞬間、622年、はるかに地味ながらも計り知れない重要性を秘めた出来事が、千マイル南の地で起こっていたのでした。メッカの地に、神の預言者ムハンマドが五十余年を過ごしていたのです。その出自と幼少期は不明瞭であり、伝説や偽典に覆われすぎていて、彼が支配部族クライシュの小さな氏族に生まれ、紀元前570年頃に貧しい家庭に生まれ、自身よりはるかに年上の未亡人との結婚で地位を確立し、後にてんかんと診断される精神障害を断続的に患ったと述べるだけで、 これらが歴史的事実と見なせるほぼ全てです。
当時のアラビアの文化水準は非常に低く、比較的高度で文明的なユダヤ教、ゾロアスター教、キリスト教は、南西端のイエメンを除いてこの地を素通りしていました。ここでユダヤ教は確立され、またここでローマ帝国はエチオピアのアクスム王朝の支配者の助けを借りてキリスト教を根付かせようと努めました。皇帝アナスタシウス1世はこれらのヒムヤール人たちに司教を派遣し、皇帝ユスティニアヌスは彼らに宣教師を送り、おそらく彼と共に法典も贈りました。しかし、ムハンマド誕生の年と近い年に、ペルシア人がイエメンに侵攻し、これらの試みは永遠に終焉を迎えることになります。
半島内の他の地域では、アラブ人は非常に原始的で統一性に欠ける偶像崇拝を行っていました。とはいえ、メッカのカーバ(立方体の家)は国民的宗教の中心と見なされる資格を多少なりとも有していたのです。そこでは他の偶像と共に、聖なる石(フェティッシュ)が崇拝者たちによって口づけされ、撫でられ、崇められていました。
ムハンマドがヒジュラ(622-32年)の10年間に成し遂げた偉大な精神的革命のうち、どれほどが彼の独創的な霊感に起因し、どれほどが外国の宗教的信念に由来するかは、再び議論の的となっています。しかし彼がユダヤ教思想、おそらくキリスト教思想にも影響を受けたことは確実であり、これらはイエメンにまだ燻る信仰の残り火の中に発見された可能性が高いでしょう。いずれにせよ彼は早くから二つの重要原則を確信していました:第一に唯一神の存在、第二に自分ムハンマドが神の預言者であること。彼が自らを世界征服を運命づけられた教団の創始者と見なしていた可能性は低いはずです。なぜなら、イエスと同様、彼自身は審判の日の差し迫りに心を奪われていたから。その日、悪人はキリスト教的な地獄へ、善人は明らかに彼自身の熱烈な想像力に由来する肉欲的な楽園へ赴くというのでした。これらの主張を確信した彼は、神の直接の啓示のもと、一連の道徳的戒律と命令を考案し始めました。それらは同時代人に広く受け入れられていたものより明らかに優れたものであり、彼の教義の中で最も価値ある部分です。彼はこの教義を数人の親族や親しい者に教え始めましたが、約10年間はほとんど成功しませんでした。市民たちは彼を無関心か疑念の目で見ており、彼の教えが広く受け入れられるようになったのは、すでに言及した出来事、すなわち622年夏にメディナへの「遷都」(ヒジュラ)を機に始まりました。ここで10年間、キリスト教の著述家が言うところの「彼の異端」は「広まり」、彼は精神的指導者であると同時に世俗的指導者としての意義を持ち始めました。後に彼の信条を近東に広めた将軍やカリフとなる有能で影響力のある人々が、彼の旗印の下に集りました。628年、彼はメッカを占領し、カーバの神殿に祀られた石の偶像を除き、正式に偶像を排除することに成功しました。4年後、彼は死にましたが、その使命は果たされていました。わずか数十年で、イスラム(「神への服従」)の波は、ペルシアとギリシャ・ローマ世界の東部・南部地域の大半を、抗しがたい勢いで飲み込んでいったのです。
こうして東方の様相を一変させ、ついでにビザンツ帝国の形と運命を決定づけたこの大革命については、その主たる影響を受けたヘラクレイオス朝とイサウリア朝の君主たちについて論じる際に、より詳細に追う必要があります。しかし、その突然かつ圧倒的な成功を理解する助けとなる、一般的性質の所見を一つ二つ述べておきましょう。内部的には、アラビア半島はムハンマドの時代に分裂し、貧窮していました。人口の大多数は互いに敵対する遊牧部族で構成され、民族的・宗教的結束をほとんど自覚していませんでした。イスラム教は、宗教的、ひいては民族的統一を提供することで、拡大の経済的必要性を実現したのです。戦場での初期のわずかな成功が、数千の遊牧民ベドウィンを旗のもとに結集させるのに十分でした。ビザンツ帝国とペルシャ帝国の双方の疲弊が残りを担い、636年と637年、両帝国はヤルムークとカーディシーヤという決定的かつ凄惨な戦場で敗北しました。
ローマ帝国の属州であるシリア、パレスチナ、エジプトには、鎌が入れられる時が訪れました。これらの地域のセム族やコプト族は、1000年にわたり、アレクサンダーの後継者たち、そしてアウグストゥスの後継者たちによって押し付けられた、ヘレニズムの支配とヘレニズム文化の下で暮らすことを余儀なくされていました。彼らの状況は決して幸福ではなく、融合も常に不完全なものでした。キリスト教の採用以来、ローマ世界を分裂させてきた宗教上の論争の多くは、人種的特徴の特殊性、そして外部から押し付けられたもうひとつのギリシャ・ローマ正統主義への順応に対する、東洋の意識的あるいは無意識的な嫌悪に起因しているといえ、シリアのヤコビ派やエジプトのコプト教徒が熱心に支持した単性論の異端は、確かに、カルケドン公会議の微妙な区別や、受肉した神の人間的要素を強調することを真に嫌悪した、一神教と神秘主義に向かう人種的、つまり東洋的な傾向を示しています。ユスティニアヌス帝の後継者たちの拙劣な政策は、こうした感情を危険なほどに煽りました。迫害の妥当性については意見が分かれるかもしれませんが、少なくとも迫害者が効果を発揮するには強靭でなければならないことは明らかなのです。マウリキオスとヘラクレイオスは多くの点で有能であったにもかかわらず、ユスティニアヌスの強大な権力ですら達成できなかった宗教的統一を、剣によって強要することの絶望性に気づかなかったのが限界でした。エルサレムのソフロニオスがあらゆる妥協を拒んだ頑固さと、正統派のアレクサンドリア総主教キュロスの残虐行為は、サラセン人襲来のまさに前夜に顕在化しました。東方諸州がローマ政府に対する人種的、ましてや国家的反感から自発的・意識的に離脱したとする見解はおそらく時代錯誤なのでしょう。しかし彼らが既存秩序の維持に何ら関心を示さなかったことは極めて確実でした。そして、厳格な一神教の教義に駆り立てられたセム系民族の大波が押し寄せた時―彼らはその教義を共有せずとも少なくとも理解でき、さらにあらゆるキリスト教信仰への宗教的寛容を約束し実践していた―彼らは抵抗することなく飲み込まれたのでした。また、東方の属州が、スラヴ人のギリシャ侵入時のように、以前には知られていなかった野蛮な異邦人の大群に浸食されたと言うのも真実ではないでしょう。むしろ逆で:サラセン人は数十年にわたりビザンツ・ペルシア国境の両側に定住しており、当時は確固たる忠誠心や独自の信仰を持たなかったため、どちらの権力にも仕え、どちらの宗教も公言していた。したがって、サラセン人による帝国の掌握は東部では迅速かつ比較的流血を伴わず、修正された勢力均衡はもはやビザンツとクテシフォンとの間ではなく、ビザンツとダマスカスとの間、そしてその後はビザンツとバグダードとの間で揺れ動くようになった――というのが正しいかと思われます。
サラセン人は好戦的な勢力であり、わずか数年でペルシア、イラク、シリア、エジプト、北アフリカ、スペインの絶対的支配者となり、強力な海軍を創設してシチリア島とクレタ島を基盤に地中海の中心部に帝国を築き、長年にわたり南イタリアの大部分を占領し、クレタ島を拠点に南ギリシャ、 アジア西海岸やエーゲ海諸島を荒らし、何世紀にもわたって毎年あるいは隔年で略奪団をビザンチンの本国中心部に送り込み、テッサロニキを略奪し、2度にわたって無数の軍勢で海陸からコンスタンティノープル自体を包囲しました。サラセン人のような好戦的な勢力が、ササン朝がかつてもたらした脅威よりも、より深刻な問題とより深遠な影響をもたらしたことは明らかでした。サラセンの勢力の拡大は、確かにバグダッド、カイロアン、コルドバといった自治的なカリフ制国家への分裂を必然的なものにしました。しかし、この分裂は、私たちが論じているこの時代において、キリスト教世界にとって決定的な利点となったことはありませんでした。サラセン人は、他のキリスト教徒に対抗するためにキリスト教勢力と同盟を結ぶこともありましたが、他のサラセン人に対抗するためにキリスト教勢力と同盟を結ぶことは嫌がりました。
7 世紀から 9 世紀にかけて、サラセン人は地中海で圧倒的な優位性を誇っていたため、ベルギーの歴史家ピレンヌは、この優位性が東西キリスト教世界の最終的な分裂の主な原因であったという説を提唱ました。彼は、東西のキリスト教世界は、単に互いに接触することができなかったのだと考えていました。もちろん、この説は大幅に誇張されていることが、今では明らかになっています。アナトリアと西洋間の海上交通は、戦争のためであれ、交渉のためであれ、商業のためであれ、完全に断絶したことは一度もありませんでした。しかし確かに危険に晒され、妨げられていたのです。そして確かに、東と西のキリスト教世界がイスラム教に対して効果的に結束することに成功しなかったのも事実でした。とはいえ、東方の皇帝の複数名がこの種の計画(東西の統一)を心に抱いていたことは確かです。
預言者の死後に勃発したアラブ軍事力の台頭は、その驚異的な速度と成功が示唆するほど計画的・組織的な作戦では決してありませんでした。632年にムハンマドが死去した時点で、彼の運動はまだ揺籃期にあり、アラビア半島内ですら普遍的な受容を得てはいなかったアラブ勢力の、初代カリフ、アブー・バクルによって完成された半島征服は、政治的異議というより宗教的異議に対する戦争でした。ローマ属州シリアへの初期の攻撃は、断片的で散発的な手法で行われ、一貫した戦略計画の存在を示唆していませんでしたた。サラセン軍が636年にヤルムーク川で完全勝利を収め、ダマスカスを二度目にして恒久的に占領したことで初めて、カリフ・ウマルは帝国的偉大さと帝国的責任の不可避性を確信したのです。
サラセン人勝利の直接的要因を求めれば、それは砂漠部族の限りない熱意と、戦場として慣れ親しんだ砂漠環境を選んだ英知にあるといえるでしょう。この地形は機動性の機会を提供し、ローマ軍団の密集陣形を不利に働かせたのです。そして確かに、ローマの将軍たちは紀元前53年にカルラエでパルティア人に世界最強の精鋭4万が壊滅した記録に、深く反省すべき材料を見出せたはずでした。とりわけ偉大な征服者ヘラクレイオス自身は、近年の研究が示すように、サラセン遠征における戦略の結果が思わせるほど愚かではなかったものの、ペルシアに対する精神的・肉体的な持続的努力の後、長い停滞と消耗の時期を経験したようでした。一方、アラブ軍は並外れた活力、進取の気性、そして天才的な将軍たちによって率いられていました。カリフ・アブー・バクルとカリフ・ウマルの将軍たち、ハーリド・イブヌル・ワリード、アブー・ウバイダ、アムル・イブン・アルアース、ムーアウィヤは、いずれも戦場において卓越した能力を持つ人物でした。
634年のシリアにおけるサラセン人遠征は、正式な侵攻というよりは試行的な性格のものであったようです。これには三つの別々のサラセン軍が参加しました。アムルはパレスチナの沿岸地帯に進入し、アブー・ウバイダは北へガリラヤ湖まで進軍しましたが、ヤルムーク川沿いのローマ要塞に阻まれました。一方、イラクで活動していたハーリドは砂漠を大胆に横断し、3月にはダマスカスの城壁下に現れました。この折、ローマ軍が敵を分割して殲滅しようとする重大な企てがあり、北から海岸沿いに進軍する強大なローマ軍が孤立したアムル軍を壊滅させようとしていることが判明したので、ハーリドはローマ軍の緩慢な作戦とは対照的な精力的な行動に出ました。彼はヤルムーク川まで後退し、既に現地に展開していたアラブ軍と合流するため、南西へ急行したのです。この作戦は成功しました。
7月、ローマ軍はガザとエルサレムの中間平野に位置するアジュナーダインで、アラブ指揮官連合軍と対峙しました。部族兵士の熱意が勝利をもたらし、ローマ軍は壊滅しました。
ヘラクレイオス帝がこれまで脅威の全容を認識していなかったとすれば、その後の数か月でそれは致命的なほど明らかとなりました。勝利したサラセン軍は北へ走ってヤルムーク川へ戻り、数か月後にはシリアの門を開くことに成功しました。ホムスとダマスカスは降伏し、ダマスカスでは征服者たちの慎重かつ賢明な統治が彼らの公約を裏付け、最終的な成功を確かなものとしました。単性論派キリスト教徒は、自らの宗教に対する寛容と礼拝の中心地への敬意を歓迎しました。実際、サラセン人征服者が「イスラム教への改宗、貢納、あるいは剣」という三つの選択肢を提示したという通説は、三つの中で彼らが圧倒的に第二の選択肢を好んだという意味で理解されねばならないものです。宗教的狂信は確かに彼らの信条の一部でしたが、強制的な改宗は含まれていませんでした。ユダヤ人であれアラブ人であれ、セム系民族は布教を好む種族ではありませんでしたが、一方、ビザンツ帝国は「彼らを強制的に改宗させる」ことを信条としていました。征服は必然的に正統キリスト教への改宗を意味し、征服された者を「一つの帝国、一つの信仰」という帝国の構想に組み込むためのものでした。これに対し、アラブ人は支配階層である「信仰者」の一員として留まることに満足し、異教徒には自身より高い税率を課すものの、それ以外は自由に信仰を執り行わせることを許しました。ローマ政府が数世紀にわたり、そして今もなお、積極的な迫害によって頻繁に宗教的強制を行使してきた地域で、こうした政策が広く知られるようになると、その影響が明らかになるのは難しくないのです。
一方、南方に残されたアムルはエルサレムを包囲しました。状況は深刻だったが、まだ絶望的ではありませんでした。実際、15年前にペルシャがパレスチナとエジプトを支配していた時と比べても劣らず、むしろ幾分希望が持てる状況ではありました。636年、アンティオキアに留まっていたヘラクレイオスは、侵略者を打ち砕くための最後にして痙攣的な試みを行いました。彼は8万人と推定される軍勢――これはおそらく誇張――を終結させました。少なくとも、アラブの首長たちが対抗するために動員できるいかなる軍勢よりも数で上回っていたことは確かです。ローマ軍には数千のアルメニア兵が含まれており、おそらくアルメニア軍団の正規テマ軍に属する者たちでした。また、キリスト教徒のアラブ騎兵からなる強力な部隊も加わっていました。財務長官テオドールスが総司令官を務めました。
この脅威に直面したアラブ軍はホムスとダマスカスから撤退し、兵力を統合して南へ70マイル(約113km)後退し、ヨルダン川の支流ヤルムーク川まで退きました。この川はガリラヤ湖とジェベル・ハウランの溶岩斜面の間にあるデラア峡谷を西へ流れていました。テオドールスの軍は緊密に追撃し峡谷を占領しましたが、その後5月から8月まで、彼らは原因不明の活動停止状態に陥りました。これが致命傷となりました。その間、アラブ指揮官たちは常の精力で行動します。増援を要請すると、襲撃や小競り合いを開始し、ビザンツ軍の陣地を東西から包囲しようとしました。ローマ軍内のアルメニア人部隊はこの停滞に不満を募らせ反乱を起こし、同胞のバーネスを最高指揮官に据えるよう要求しました。ついにアラブ軍の西進はワディ・アル=ラッカド川に架かる橋まで到達し占拠しました。この橋はビザンツ軍の後方、北との連絡線の一つを遮断する位置にありました。決定的瞬間は8月20日に訪れました。南から砂嵐が吹き荒れ、ローマ軍兵士の顔面に吹きつけたのです。猛々しいサラセン人たちはこの隙を突いてローマ軍陣地に突撃。陣地は崩れ、兵士たちは逃げ場のない位置に追い詰められました。彼らはほぼ全滅し、テオドールスも戦死者の一人となりました。
636年8月20日、ヤルムーク河畔の戦いで名高い決戦の結果、シリアの運命は決定的に決しました。それだけでなく、ペルシアやエジプトの運命までもが定まったのです。老いて病に伏した皇帝は、おそらくすでにその恐ろしい病に蝕まれていたのでしょう——その病が最終的に彼の命を奪うことになります——東方を放棄し、7年前に凱旋して入った首都へと引き返しました。この撤退の際、ヘラクリウスは「シリアよさらば」と口にしたと言われます。
戦場での抵抗はもはや不可能となりました。ホムスとダマスカスはアラブ軍に再占領されました。攻略困難な要塞エルサレムは、ソフロニオス総主教によって守られていました。彼の頑固な偏狭さが、「一つの意志と一つの力」による解決で宗教的分裂を終結させる望みを打ち砕いていたのですが。637年の秋までに、聖都が降伏せざるを得ないことを彼は悟らざるを得ませんでした。アラブ側は、キリスト教の礼拝と教会への敬意を示すという、彼らの常套的な寛大な条件で講和する用意がありましたが、しかしソフロニオスは、カリフ本人とのみ合意を結ぶと主張しました。奇妙なことに、この尊厳ある人物(ウマル)はメディナから自ら旅立ったのです(実際には、このウマルは彼のいとこで容姿がそっくりだったハーリドであったという説がある)。その粗末な継ぎはぎの外套をまとった姿(メディナのカリフはダマスカスやバグダードの後継者とは異なり、預言者の厳格で質素な統治様式を守っていた)で現れたという話は、ギリシャの史料からよく知られており、疑う余地はなありません。カリフ・ウマルは都に入り、礼儀正しい総主教に導かれて遺跡を巡りました。総主教は彼の馬の手綱を握りながら、この新たな東方支配者のぼろぼろの服装に密かに嫌悪感を抱いていました。そして聖墳墓教会で客人を見たとき、彼はこう叫んだと言われます。「見よ、預言者ダニエルの口を通して語られた荒廃の忌むべきものが、聖なる場所に立っている」
エルサレムの降伏に先立ち、ユーフラテス川沿いのカーディシーヤで、征服者ハーリド(誤。正しくはサアド・イブン・アビー・ワッカァス)と若きヤスタゲルド王のペルシャ軍司令官ルスタムとの間で戦闘が起きました。この戦いは、その長さと激しさにおいてアジュナーダインやヤルムークの戦いをもはるかに凌いぎました。しかし結局、サラセン軍はいつものように完全勝利を収め、ペルシャは必然的にシリアと同様に彼らの支配下に入りました。
エジプト侵攻は、ビザンツ帝国が依然として相当な陸海軍を運用可能な地域でしたが、638年にエルサレムでカリフ・ウマルと将軍アムルとの間で合意されたもののようです。しかしアムルがエジプトに侵攻したのは639年末になってからでした。その兵力は作戦遂行には明らかに不十分でした。しかしながら、ベドウィン戦士の名声とビザンツ指導部の脆弱さが、数多の兵力を補いました。ペルシウスは一ヶ月で陥落し、ナイル川デルタの要衝にある堅固な要塞バビロンは、持ちこたえそうに見えました。ただし、要塞にいたアレクサンドリア総主教キュロスが意気消沈し、641年2月のヘラクリウス帝の死報が士気を完全に喪失させてしまいました。要塞は4月に降伏しました。強固で豊かな都市アレクサンドリアは、ビザンツが海を支配する限り何年も持ちこたえ得たはずですが、まず休戦交渉を行い、642年9月に占領されました。

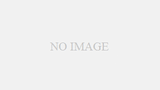
コメント