「歴史上初めて、中央集権化の思想が政治に導入された…」
ティグラト・ピレセル三世(紀元前744年—727年)
ティグラト・ピレセル三世は、一般的にアッシリア史上最高の王であり、古代世界でも最も成功した軍事指揮官の一人と見なされている。彼は、それまでのアッシリア王たちが築いた緩やかな覇権体制を、史上初の中央集権的な帝国国家へと置き換える過程を開始した。この帝国は、後のあらゆる帝国のモデルとなった。同時に彼はアッシリア軍を再編成し、歩兵と騎兵が連携して行動する「複合兵科」の使用を導入した。
これらの主張を理解するには、ある程度の歴史的背景が必要である。古代史に多少の知識がある読者なら、ティグラト・ピレセル3世より千年以上も前から中東に巨大な帝国が存在していたことをご存知だろう。征服に基づく最初の真の帝国はアッカドのサルゴンによって築かれた。彼は青銅器時代初期(紀元前3千年紀末)にメソポタミアのほぼ全域を統一し、シュメールとアッカドとして知られる国家を形成した。青銅器時代後期(紀元前2千年紀)には、新王国時代のエジプト人、アナトリアのヒッタイト人、そして主要国家がメソポタミア北部とシリアに存在したミタンニ王国であったフルリ人らによって、同規模の帝国国家が形成された。しかしこれらは後のアッシリア帝国のような中央集権的帝国ではなかった。むしろ覇権国家と表現するのが適切である。成功した王たちが近隣諸国を服従させ城壁を破壊させ貢ぎ物を納めさせたことで成立したが、これらの小国の土着王朝は置き換えられず、貢ぎ物を納め要塞再建を試みない限り、宗主国からの干渉はほとんど受けなかった。青銅器時代、このような国家は「大王国」と呼ばれ、他の王を支配する者は自らを大王と称することができた。当然ながら従属王たちは信頼に足らず、彼らを従わせるために懲罰遠征を派遣する必要が頻繁にあった。
アッシリアはティグラト・ピレセル3世以前にも、断続的にこの意味での大王国であった。紀元前14世紀、中アッシリア王国は北メソポタミア全域の統一に成功した(「中アッシリア」は青銅器時代後期のアッシリアで話されたアッカド語の方言を指す言語学的用語である)。ティグラト・ピレセル1世(紀元前1114-1076年)のもとで最後の拡大期を迎え、バビロンを陥落させ、アナトリアとイランの奥地まで侵攻した。その後、シリア砂漠から移住してきたアラム人部族によってアッシリアは荒廃した。彼らはおそらく、輸送手段としてアラビアラクダを初めて完全に活用した民族であった。紀元前10世紀、アッシリア王国は原初の故郷へ押し戻された。それはティグリス川上流に沿った100マイルの帯状地帯で、アッシュル(古代の宗教的首都)、ニムルド(王都)、ニネヴェ(紀元前700年以降の主要王都)、アルビルといった都市を含む地域であった。883年から824年にかけて第二の拡大期が訪れ、精力的な二人の王、アッシュルナシルパル2世とその息子シャルマネセル3世がアラム諸侯国を征服し、北メソポタミアにおけるアッシリアの支配を回復、さらにシリア北部まで広がる属国群を確立した。これは中アッシリア国家や青銅器時代の他の大国と同様に緩やかに組織された覇権構造であり、長くは続かなかった。紀元前824年から744年にかけては弱体な王が相次ぎ、属国王たちは離反した。しかしこの衰退期においても、アッシリアは北メソポタミアの支配を維持し続けた。その支配域はティグリス川とユーフラテス川に挟まれた平原全域(西はユーフラテス川の大曲がりまで)と、東はザグロス山脈の麓まで及んでいた。
紀元前744年、こうした弱体な王たちの最後の一人が反乱によって打倒され、アッシリアの首都ニムルドの総督が王位を奪取した。彼は先代の王の子孫であると主張したが、これは疑わしい。アッシリアの伝統は、紀元前1500年頃から途絶えることなく同じ王家から全ての王が生まれたという神話を尊び、書記たちは継承の断絶を隠蔽する傾向にあった。ニムルド総督の真の名は不明である。ティグラト・ピレセルは、アッカド語の王位名トゥクルティ・アピル・エシャルラ(「わが信頼はエシャルラ[神ニヌルタ]の子にある」の意)の聖書的翻字である。この名前の選択は、拡大政策を意図的に宣言するものであった。彼は、それまでのどの王よりもアッシリアの軍勢を遠くまで進めた英雄王ティグラト・ピレセル1世に因んで自らを名乗ったのである。
ティグラト・ピレセル3世の遠征
この時代の記録資料——碑文、年代記、王室文書、条約、聖書の一部——は、アッシリア史の他の初期時代に比べ極めて豊富であり、征服遠征の比較的完全な再構築を可能にしている。
紀元前744年に権力を掌握すると直ちに、ティグラト・ピレセルはバビロニア(メソポタミア南部)への遠征を指揮した。これは同盟者であるバビロニア王ナボナッサル(ナブ・ナシル)を、南西イランのエラム王国に支援された反乱を起こしたアラム族とカルデア族から守るためであった。アッシリアは今や、豊かで戦略的なバビロニアの支配権をめぐりエラム人と対峙した。ナボナッサルはその後10年間バビロンの王位を維持したが、この時からティグラト・ピレセルの属王となった。
しかし、アッシリアに対する主な脅威は、真北に位置するアルメニア山脈のウラルトゥ王国から生じていた。ウラルトゥの人々の民族的・言語的親和性は定かではない。彼らはフルリ人かアルメニア人であった可能性があり、あるいは西アナトリアから移住してきたアルメニア人を支配する、より古いフルリ人エリート層であったかもしれない。(人口にアルメニア層が存在したと推測される主な理由は、紀元前6世紀にウラルトゥがアルメニア王国に取って代わられたことにある。)紀元前8世紀初頭、ウラルトゥはアッシリアと同規模の王国へと成長し、北シリアから南西アナトリアを経て西イランに至る同盟国群を形成した。この巨大な三日月形の同盟圏はアッシリアの北境を包囲し、東西交易路の要所を掌握したのである。年代は不確かだが、紀元前743年頃、アッシリア王がウルルトゥの同盟国であるアルパド市を首班とするシリア諸侯連合を攻撃したようだ。翌年、ウルルトゥのサルドゥリ3世はユーフラテス川上流のコマゲネの戦いでアッシリア軍に敗北し、その後レバントの同盟国を見捨てた。紀元前740年、アルパドは3年にわたる包囲戦の末に陥落し、シリア北部の大部分がアッシリアに併合された。ダマスカスとイスラエルの王たちは貢ぎ物を捧げることを申し出た。
紀元前737年から736年にかけて、アッシリア王は東進し、中央ザグロス山脈を占領、メディアを横断して進軍し、メソポタミアの支配者がこれまで到達したことのないほど深くイラン高原に侵入した。紀元前735年、彼は北へ進路を変え、ウルルトゥ自体を侵略した。険しいアルメニア山脈を越え、ヴァン湖畔にあるウルルトゥの首都トゥシュパ(現在のヴァン)を包囲した。包囲は失敗に終わったが、ウルルトゥが近東情勢で果たす役割は大幅に縮小された。
紀元前734年から732年にかけて、レバント地方における第二の定住が必要となった。アシュケロンとガザのペリシテ人支配者たちはアッシリアに対抗するパレスチナ都市同盟を結成したが、ティグラト・ピレセルに敗北した。アモン、エドム、モアブ、ユダ、そしてアラブの女王が貢ぎ物を納めた。紀元前732年、ユダ王アハズはイスラエルとダマスカスに攻撃され、アッシリアに援軍を要請した。ティグラト・ピレセルはダマスカスとイスラエルの半国を併合し、両者を属州に分割したが、イスラエルには傀儡王ホシェアを残した。ユダとペリシテ諸都市はアッシリアの属国となった。
アッシリアの王たちは、血なまぐさい碑文で自らの勝利を誇示するのが常であった。以下はニムルドのティグラト・ピレセル宮殿から出土した碑文の一節で、ダマスコのレジン王とイスラエルのペカ王に対する勝利を称えるものである:
ダマスコのレジンは…その戦士たちの血で川を赤く染めた…あいつ[レジン]は命を救うため独り逃げ延び、マングースのように城門をくぐった。私はその重臣を生きたまま串刺しにした…鳥を籠に閉じ込めるように彼を監禁した。彼の庭園…数えきれない果樹園を私は切り倒し、一つも残さなかった。[十六]のビット・フムリ[イスラエル]の地区を、私は地面に平らげた。
アッシリアの征服は預言者イザヤに宇宙的な歴史観を喚起し、それはユダヤ・キリスト教伝統に多大な影響を及ぼすこととなった。あらゆる歴史的出来事は神の計画の一部と見なされた。アッシリアは神の鞭、イスラエルの民の罪を罰する道具であった:
アッシリアよ!彼はわが怒りの杖、わが憤りの杖をその手に持つ。わが怒りを招く民、わが怒りを煽る国(イスラエル)に、彼を遣わし、略奪し、蹂躙し、街路の泥のように踏み潰すためである。イザヤ書10:5-6
その後、バビロニアの最終的な平定が行われた。ナボナッサルは紀元前734年に死去し、731年にはカルデア人の簒奪者がバビロンを掌握した。ティグラト・ピレセルは南部に侵攻し、簒奪者を殺害。729年または728年には「プル」(聖書で彼を指す呼称)の王位名のもとバビロニア王の称号を称した。
数百万の人々がアッシリア帝国の支配下に組み込まれた。地中海に至る新たな属州群が創設された。これらの属州の外縁では、南アナトリアからエジプト国境に至るまで、厳重に統制された従属国家群が連なっていた。バビロニアはアッシリアの直接支配下に置かれた。主要なキャラバン路の終着点もアッシリアの掌握下にあった。これは人類が当時までに生み出した最大かつ最も複雑な政治構造であった。
新たなアッシリア帝国主義の顕著な特徴は、征服された住民から数万人単位での大規模な移住強制であった。中東では以前から行われていたが、ティグラト・ピレセルが開始したような大規模なものは前例がなかった。彼によって数万人が移住させられ、この政策は後継者全員によって継続されたため、紀元前612年のアッシリア帝国終焉までに、王の碑文を信じるならば、400万人以上が移住させられた。この政策の目的は、当然ながら「反乱」への懲罰と、不忠実な住民を分散させることで将来の反乱を未然に防ぐことにあったが、同時に農業労働力やその他の人材を確保するためでもあった。宮廷の需要を満たした後、移送された人々は神殿、貴族、都市に配分された。大多数は家族単位でまとめられ、小規模な共同体に定住させられた。彼らはアッシリア人として扱われ、碑文には繰り返し「我は(追放者を)連れ去り、彼らを定住させた。アッシリア人として数え、主なるアシュル(アッシリアの主神)の軛をアッシリア人同様にかけ、貢ぎ物と税をアッシリア人同様にかけた」との記述が見られる。彼らは最終的にアッシリア王の忠実な臣民となることが想定されており、実際にそうなった例も数多く確認されている。彼らの大半はアラム語圏出身であり、これは既にかなり進んでいたメソポタミアのアラム語化をさらに促進する一因となった。
行政改革
征服が進むにつれ、王は旧貴族に代わる新たなアッシリアのエリート層を育成し始めた。領土を分割して州の数を約80まで増やすことで貴族の権力を制限し、個々の総督の権限を縮小した。多くの宦官が総督に任命されたのは、彼らが家族を持たず、完全に王に依存していたためである。各州はシャクヌ(「任命された者」)またはベル・ピハティ(「地区長」)と呼ばれる総督によって統治された。彼らの職務は秩序維持、貢納徴収、王とその随行者・軍隊の通過時の物資供給、必要に応じた兵士や労働班の提供であった。徴兵制度は古代中東で広く用いられた方式であった:個人は土地の授与(イルクム)を受ける代わりに、必要に応じて一定数の兵士や労働者を王に供給することを条件とした。前述のように、その多くは移住させられた者たちから調達された。帝国には大規模な道路網が張り巡らされ、その利用は王印を携行する者に限定されていた。朝廷は史上初の効率的な郵便制度を通じて総督らと連絡を保ち、これは後にペルシアの有名な郵便制度のモデルとなった。王はまたクルブトゥ(qurbutu)と呼ばれる少数の信頼できる行政官を配下に置き、彼らは定期的に諸州を視察し、直接王に報告を行った。多くの属国は州に編入され、独立を維持した国々は監督官(ケプ)の管理下に置かれた。貢納の怠慢やその他の不忠の兆候は、独立の喪失と州制への編入を招いた。ティグラト・ピレセルの後継者たちによって継続されたこれらの改革の意図された結果は、王権の著しい強化であった。
軍事改革
旧軍はサブ・シャリと呼ばれ、イルクム保有者と地主が提供する農民徴兵で構成され、地方総督の指揮下で帝国全土に配置されていた。活動は夏の期間、6月の収穫期から10月の種まき期までの間のみ行われた。基本単位はキスル(kisru)で、「コホート」と訳されることもあり、ラブ・キスリ(rab kisri)が指揮を執った。ラブ・キスリの下には五十人隊長と十人隊長が配置されていた。五十人を超える部隊が存在しなかったことは、キスルがローマのコホート(600人)と同規模であったという仮説を支持する。この場合、ラブ・キスリは現代の大佐に相当する。ティグラト・ピレセル王はおそらく、王の直轄下にある常備精鋭部隊、いわゆる近衛隊(kisir sharruti)と、さらに小規模でより精鋭な王室親衛隊(sha qurbuti)を追加した。
これらの部隊は全て同種の装備を保持し、歩兵・騎兵・戦車兵を包含していた。兵員は全てアッシリア人出身者から徴募された(この時点ではアッシリア人とアラム人の混血集団であったことに留意すべきである)。アッシリア国家は9世紀に北メソポタミアのアラム人を同化することで拡大し、ティグラト・ピレセルによるアラム人の大規模な追放はアラム化のプロセスを継続させた。その結果、アッシリア帝国末期には、メソポタミアの共通語としてアッカド語に代わってアラム語が使用されるようになった。) この頃、非アッシリア人補助兵(主に純粋な部族系アラム人)が軽歩兵として大量に徴用され、弓兵や槍兵として武装した。国境の属国から派遣された同盟軍部隊も多く、各々の伝統装備を使用していた。ティグラト・ピレセルが動員可能な総兵力は50万人に達したと推定される。
ザムアの文書には、紀元前8世紀後半の地方総督指揮下のサブ・シャリ部隊の兵力内訳が記されている:戦車10台、騎兵97名、アッシリア重歩兵80名、補助弓兵440名、補助槍兵360名。さらにアッシリア人従者101名と、騎兵部隊に随行する馬丁やその他の補助要員がいた。興味深いことに、総督が配した槍兵と弓兵の数はそれぞれ440名で完全に一致していた(重装のアッシリア槍兵と軽装のアラム槍兵を合わせて)。これらは概算値であった可能性が高いが、槍兵と弓兵の数を均等にするのが理想とされていた点は依然として重要である。
この新型軍隊は通年作戦が可能であった。戦役時には王親衛隊と王近衛隊が軍の中核をなし、総督が提供したサブ・シャリ部隊や必要に応じた同盟軍部隊が支援した。通常は王自らが指揮を執ったが、左翼元帥と右翼元帥の二名の野戦元帥(トゥルタヌ)も存在した
騎兵はこの軍隊の偉大な革新であった。以前のアッシリア軍は青銅器時代の遺物である戦車に依存していた。しかし紀元前10世紀のある時期、ユーラシア草原の遊牧民が騎馬術を習得した。アッシリア騎兵が初めて記録に登場するのは紀元前853年だが、当時は戦車部隊と連携して運用されていた。鐙のない馬の制御技術が未熟だったため、騎兵は二頭立てで行動し、一人が手綱を握り、もう一人が弓を射る方式を取っていた。ティグラト・ピレセルの時代には、アッシリア騎兵は単独騎乗となり、各騎兵は弓または槍、あるいは両方を装備した。戦車は高位の将校の威信を示す乗り物としてのみ残され、実用性は失われた。
新軍の最も恐るべき戦力は攻城兵器であった。アッシリア人は攻城戦の技術を極限まで高め、この水準は紀元前4世紀にギリシャ人がカタパルトを発明するまで破られることはなかった。主な革新は9世紀に発明された破城槌であり、これにより都市を強襲で陥落させることが可能となった。一部の都市は一日ほどでアッシリアに陥落したが、前述の通りアルパドは三年持ちこたえた。
アッシリアの碑文には現実的な戦闘描写は含まれておらず、アッシリア美術はエジプト美術とは異なり、隊列を組んだ兵士を決して描かない。紀元前1275年にエジプト人とヒッタイト人の間で戦われたカデシュの戦いを我々が再構築しようとするように、アッシリアの戦いを再構築することは不可能である。アッシリア軍が基本的に歩兵軍であったことは明らかである:ザムアでの歩兵と騎兵の比率は8対1であった。ニネヴェのアッシュルバニパル宮殿から出土した紀元前653年のウライ川戦いを描くレリーフ(アッシリア美術で最も優れた戦闘場面)は、槍兵と弓兵の連携を示しているように見え、おそらく近世ヨーロッパにおける槍兵と銃兵の連携に似ている。重装歩兵の援護下で弓兵が戦闘を開始し、接近戦となれば盾の後ろに退却する様子が想像される。戦いはおそらく弓術によって決着した。騎兵は歩兵を支援し、矢で敵を撹乱し、敵が崩れた際には逃走する敵を追撃するために突撃したであろう。
アッシリアの戦争様式については不明な点が多いものの、様々な兵科が戦場で異なる役割を担い相互に支援する「兵科混成」を初めて実現した戦争形態であったことは疑いない。つまり、ギリシャやローマが知ったような真の戦術を駆使できる最初の軍隊であったと言える。

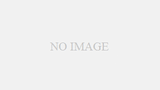
コメント