義経(一一五九―一一八九)
日本の将軍。主立った戦争は源平合戦。合戦中の戦役は一ノ谷、八島と壇ノ浦、一一八九年の衣川。
一一五九年、源義朝と常盤御前の間に生まれる。幼名は牛若。上に今若、乙若がおり、さらにその上に異母兄が二人ある。源平合戦の折父義朝が平氏に敗れた際、義朝は常磐に身を隠すよう伝えたが、情愛の濃い常磐は結局どこにも逃げず、それから九日後、義朝が長田忠致に討たれたことを知ったて悲しみに暮れ、ただ一人このとき二歳の牛若を抱いて清水寺に向かった。四〇日ほどののち鎌倉御曹司頼朝の助命が確定してから六波羅に出頭、子供の命だけは助けて欲しいと願い出る。これを引見した平清盛はその美貌と心根に心を動かされ、常磐と三人の息子全員の助命を約した。常磐は清盛の妾となったが一子を生んでから寵愛衰え、そののち一条大蔵卿の妻となるという数奇な運命をたどる。牛若は少々成長するまで清盛のもとで養育され、しかるのち鞍馬寺に入れられて名を遮那王と改められるが、十一歳になるまで自分の出自を知らず、平家の子だと信じていた。がしかし、その年遮那王は偶然の機会に系図を見て自分の出自を知り、以来父祖の仇を討ち平家を打倒するため、書を読みふけり武技を練る日々が始まったという。この頃の武芸修行で天狗に兵法を習ったというのは当然民間伝説で信じるに足りないが、彼がのちに見せた常人離れした活躍とその戦術を見るにそう言う話が出てもおかしくないところではあった。十六歳の時奥州に行った。その理由の一つは祖先たる八幡太郎義家の深い関係がある土地であることと、もう一つには当時の奥州藤原家が一種の独立国家で平治や朝廷の権威の外にあったから、ここで時節到来まで雌伏の時を過ごそうと考えたからであろうと推察されている。旅費のない遮那王は金売吉次にたのんで奥州に向かい、道中深栖頼重を家臣に加え、近江の鏡の宿で自ら元服、ここに源九郎義経と名乗る。やがて奥州平泉に到着、藤原秀衡は喜んで義経一行を迎えた。このとき義経一七歳。こののち五年間彼は奥州にいたが、その間のことを伝える資料は全くない。ただこの当時に佐藤継信、忠信兄弟、伊勢義盛、堀景光らと出会い主従関係を結んだであろう事は想像に難くない。そして一一八〇年、義経の異母兄・頼朝が挙兵し、しかし石橋山で平家の軍に敗北したことは奥州にも聞こえた。義経はこれぞ機会とばかりに立ち上がり、関東に向かったのだが、頼朝挙兵を知ってからそのもとにはせ参じるまでが長すぎる(石橋山での敗戦が八月二三日、勢力回復しての再決起が九月一九日で、義経が頼朝のもとに駆けつけたのはそれから一ヶ月も後の一〇月二一日)。秀衡からしばらく様子を見よといわれたというが、実際には兵を借り受けようとして交渉に粘ったのだろうというのが海音寺潮五郎氏の見解である。さておき、一〇月二〇日に平家の大軍を破った頼朝は黄瀬川まで来て当地で宿泊したが、その旅宿に突然「二十歳そこそこで色白、小柄で顔立ちは目つきが鋭すぎる」男がやってきて、鎌倉殿に見参したいと申し入れた。そこに居合わせた頼朝譜代の家臣たちにとってみれば明らかに不審者であり、それをさておいても不遜である。これがために義経は後々、板東武者たちから白眼視されることになる。それから四年が経過して一一八四年、義経らの縁者木曽義仲が、平家を西に追いおとした功績を鼻にかけて京都で野放図に振る舞い、源氏の評判を落とした。義経は義仲の行状調査のため京都に向かったが疑われて入ることが出来ず、伊勢に引き返して逗留。その間義仲は猖獗を極め、一一月一九日法王の御所法住寺を焼き、法王を捕らえ後鳥羽天皇をも閑院殿におしこめた。義経はこれらの報告を北面の武士橘公朝ほかより聞き知り、飛脚によって鎌倉の頼朝にその事実を伝えた。頼朝は「逆賊を討つ」という大義の下義経と範頼に兵六万を与え、西に向かわせることにした。六万のうち義経が率いた兵は二万五千。川岸に拠る義仲の防衛線を見た義経は即座に戦術を策定、川岸沿いの民衆を立ち退かせた後で火をかけて焼き払い、全軍を展開、岸近くに高い櫓を作らせその櫓上から全軍に布告し、兵士たちを高揚させたという。はじめ義経の軍は攻めあぐねたが勇士佐々木高綱と梶原景季が相次いで激流に身を投じ、これに全軍が続いて義仲の軍をさんざんに破ったという。この敗戦で義仲は京へ退却、翌日粟津の戦いで戦死した。それから間を置かずして一の谷の戦いとなる。一一八五年二月五日、一ノ谷へ向かうべく丹波路を執った義経はその道中、丹波・摂津・播磨三国の境上の三草山で平資盛、明盛が七千余で布陣していることを知り、夜半、奇襲をかけてこれを破った。その翌日、土井実平と田代信綱に兵を授け、「明日卯の刻に一ノ谷の門を攻めよ。われらはひよどりごえして敵の背後から襲うであろう」と言って、自らは熟練の騎馬隊を選抜して山を越え谷を駆けて、東西の門からの源氏勢の攻撃を良く防いでいた平家軍を、少々信じられないような戦術機動によって険な峠を越え、鉄拐が峰の急斜面を逆落としに駆け下りて、平家軍の後背に火を放ち、周章狼狽する敵を一挙覆滅したのである。騎兵を打撃力として使ったわけではないが、この用兵の妙は世界戦史上でも指折りのものと言って良い。特に誰も予想できないところから、最も効果的なタイミングで絶妙の攻撃を仕掛けたのは秀逸であった。同年九月、頼朝は平家追討の令を出した。ただしこれは範頼だけに命じて義経は外されている。これ以上の偉功を立てた義経が自分の脅威になるかもしれないという頼朝の猜疑心故の措置だったが、素直だが傲慢倨傲で政治感覚に乏しい義経は、自分が頼朝に疎まれていることにも源氏諸勢力から侮られていることも理解できていなかった。さておいて範頼は出陣したが、備前の児島というところで平行盛を敗走させた以上のことをしていない。その間屋島の平家大本営は復活の準備を着々と整えていた。頼朝自身が身一つから源氏を再興したのだから平氏に逆王手をかけられる可能性も大いに考えられる。とにかく範頼の失敗によって、戦場に出られず不遇ながらこの時期美しく気性の良い河越重頼の娘を娶ってそちらでは充実していた義経を、頼朝はしぶしぶながら起用する気になった。義経は兄の信頼を回復したと思い有頂天になり、わずか五〇〇人ほどで四国・屋島に出陣。一一八六年二月二六日船の用意が出来て出帆したが、不吉な大風で引き戻され、あまつさえ多数の船が破損した。止まって船を修理し終えると今度は激しい北風が吹き、船頭らは震えて出帆をためらったが義経が「すわ、汝ら朝敵ぞ!」と言って彼らを殺さんばかりだったので船頭らは必死に船を漕ぎ矢のように進んだ。義経は屋島近辺に上陸し、牟礼、高松、屋島と奇襲に次ぐ奇襲で立て続けに抜いた。平氏はまたもや周章狼狽して船で海上に逃れ、九州を目指したが、範頼のため上陸できずに馬関海峡彦島に拠った。屋島の戦いから一ヶ月、義経は改めて船を支度したが、その間思いも掛けぬ人物が参謀というか副将として義経のもとに派遣された。梶原景時、常に義経を軽侮し憎悪すらしていた存在であるが、頼朝の命令で嫌々やってきた。義経としても邪魔なだけだったであろう。ちなみに義経が、というより源氏の力が集めた船は八四〇余艘、平家方は五〇〇余艘だったという。しかし中国の南船北馬と同じく、日本においては西が水軍、東が陸軍である。数の優位だけでは気の抜けるところではない。決戦は3月24日。戦闘は正午から午後4時頃にかけての短時間で行われ、潮流が自軍有利になったところを見澄ましての、義経の鮮やかな勝利であった。戦闘が源氏優勢となったときにすかさず裏切った田中成良と彼に従う船実に三〇〇余艘がなければまだ勝利は確定しなかったかもしれないが、それでも義経の勝利の勝ちは揺るがない。しかしこの勝利が彼の栄光の絶頂であった。頼朝の義経憎しの感情は加速度的に増していき、義経はその理由が最後まで分からないままに毎回身の処し方を違え、潔白を証明するため鎌倉に嘆願に赴くも許されず、政治的に孤立させられ、ついには鎌倉の軍隊に追われ奥州に逃れる。奥州の主秀衡は喜んで義経を迎え、いずれ源氏と藤原氏が対立関係となった才に切り札として彼の軍事的才能を使うべく厚遇したが、やがて秀衡が詩に泰衡に代わると状況は一変、義経の身柄引き渡しを要求する頼朝からの恫喝に耐えかね、また義経が相も変わらず尊大で野放図であったために、一一八九年四月三〇日、泰衡は兵数百を以て衣川の居館を襲撃し、義経を殺した。享年三一歳。
彼は日本最大の民族英雄の一人であり、軍事的天才である。その活躍は事実を超えて大衆文学に誇張されている部分も多いが、戦えば必らず勝ち、しかも寡をもって衆に勝った。その輝かしい勝利と偉功にもかかわらず彼は悲惨で不幸な最後をたどったが、それもまた究極的には彼が天才であるが故に仕方のないことであったとすら言える。指揮官としての彼は世界史上の偉大な名将に劣らず非凡で精力的で、剛胆であったが、なにより彼にとって不幸だったのは兄・頼朝が彼の努力や忠義、そして勝利というものになんらの恩も感じないどころか、かえってそれを憎んだところにあるであろう。
源義経
 日本史
日本史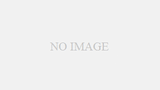
コメント