源義家(みなもとのよしいえ。一〇三九?-一一〇六)
清和源氏の諸流のうちで、のちに武門の棟梁として仰がれることになるのは源満仲の第三子・頼信を祖とする河内源氏である。この河内源氏に武家としての発展の基礎を築いたのは平忠常の乱で功を上げた源頼信、その嫡子で前九年の役を戦った頼義、そして本稿の主役、八幡太郎源義家である。
義家は源頼義と平直方の娘の間に生まれた。幼名は不動丸、源太丸などといい、のち石清水八幡宮の宝前で元服して八幡太郎を称する。「陸奥話記」によればこの直方が騎射に優れていたことからその娘をめあわせたと言い、彼女は三男二女を産んだが、その嫡子が義家であった。義家の生年には諸説あり正確を期することが出来ないが、およそ長暦三年(一〇三九)前後のことと推定される。
河内源氏の根拠地は河内国古市郡壺井郷一帯であったと言うから、義家もこの地に生まれたかと思われる。しかし彼の少年、青年時代について確たる所伝は残っていないので、彼がどのような環境のもとに成長したかは定かではない。「世界と日本の歴史 8」は頼信の嫡孫にして頼義の嫡子として、多数の家人達の間で暖かく養育され、自由奔放な、また自由な時期を過ごしたのではなかろうかというがそれも想像でしかない。もっとも後年見せる武勇将略の素地を作ったのがこの時期であろうことは想像に難くない。
祖父・頼信が世を去ったのは義家十歳の時であったと伝わる。武将としての素養を祖父から開け継いだ義家は、その日常の立ち居振る舞いからも大いに影響を受けたらしい。この時期すでに地方の治安は乱れがちであり、実力のみが治安を守る手段となってた。義家の住まう南河内一帯は安穏であったが、それはこの地方の実力者として君臨していた河内源氏一族の力によってなされていたものであり、源氏の力が弱まれば覆る脆弱な基盤でしかなかった。こうした現状に対する認識とともに、現地の支配者としての自覚も、徐々に義家の心の内に芽生えていった。
義家が成長した時代は、いわゆる摂関政治がその最盛期を過ぎて衰退期に入り、やがて院政の時代へと移りつつある時期であった。そして貴族たちは、すでにその周囲に武士をおいて自らを守り、また武力を利用してその政治権力を維持しようとしていた。
こうした中央貴族の武力は、初めは地方農村出身の武士を直接に京都に招いてくるということはせず、彼ら貴族たちの仲間のうちで比較的多く武家的要素を持ったもの、武技に優れたもの等を中心とするものであった。そうした武人的性格を持つ者が、地方武士たちを私的な従者、すなわち郎等、郎従として引き連れ、朝廷や上級貴族たちを警護したのである。彼らは衛府、馬寮などの官人や、検非違使といった「武官」に任ぜられることが多く、京において「武者」と呼ばれた。河内源氏は、そうした武者の代表的な存在であった。
義家の父頼義は、諸国の守を歴任した程であるから、身分的には中級貴族に属する。しかし、彼はそのほか左衛門尉、兵庫助、左近将監、左馬助など、おもとして武官系の官職にも任ぜられている。彼は国司として地方に赴任したとき以外は主に京都にいて、時としてその本拠地である南河内との間を往復するという生活をつづけたものと思われる。義家も父について京にのぼり、そこで生活するという時期もあったであろう。父の「武者」としての生活に接しながら、義家もやがて同じ武者となり、人々から「武勇の士」として畏敬の目で見られる人物となるべき修練を積んだ。そして、彼自身もやがて父頼義とほぼ同様な官職を歴任する。それはまさに「武者」にふさわしい経歴といえよう。
こうして義家は、はじめから「武者」たるべきことを運命づけられ、またその道を歩んだのであった。そして彼が武将として歴史の上にはっきりとその姿を現すのは、永正六年(一〇五一)にはじまった、前九年の役の時である。彼は父陸奥守頼義に従って奥羽の地に転戦し、大いに武功をあらわしたのであった。この時、彼は十九歳であったが、その奮戦ぶりは人々の目を奪った。「陸奥話記」は最大の賛辞を持って彼の活躍を次のように語っている。それは、黄海の戦いで頼義の軍が、風雪の中で大敗を喫した時のことである。
将軍の長男義家は驍勇絶倫にして騎射神のごとし。白刃を冒して重囲を突き、賊の左右にでて、大鏃の箭をもって頻りに賊帥を射る。矢は空発せず当るところ必ず斃す。雷奔風飛、神武命世、夷人靡き走り、あえて当たるものなし。
前九年の役の勝利によって、義家は合戦の賞与として従五位下にのぼり、出羽守。しかしこの拝任を不満として彼は越中守への転任を願い出ている。僻地の出羽に赴任することを喜ばなかったためらしい。この希望は受け入れられなかったが、その後数年の延久二年(一〇七〇)、下野守とされる。この当時陸奥では治安乱れ、公事を拒否したりかんぶつを横領したりする土豪が増え、騒乱を繰り返した。その代表たるものが藤原基通で、陸奥守源頼俊はこれと合戦して敗れるというていたらく。下野守として現地にあった義家は自ら朝廷に願って頼俊を助ける兵を出し、基通を降伏させる。これもまた、義家の武名を揚げた。
これから五年後、父頼義が八十八歳の高齢で世を去った。嫡流を継いだ義家はすでに三十七歳、これまでの合戦でその名と評価は極めて高く、「武勇第一の人」と言う地位をもって衆目の一致するところとなっていた。さらに祖父以来の豊かな財政基盤は彼自身の任上での蓄積を併せてさらに膨れあがり、名実ともに武家の棟梁としての地位を確立しているといえた。彼自身が優れた武将であるだけで無く、強力な郎等、郎従を多く従えていたのだから比類なし、という威勢もうなずける。よって朝廷でも、武力を必要とする際には第一に義家を考えるのが当然となっていた。
承暦三年(一〇七九)八月、美濃で源重宗の追討を命ぜられたり、二年後の永保一年九月には延暦寺と園城寺の争いに際して検非違使とともに園城寺に派遣され、乱暴狼藉の僧兵拿捕を命ぜられたりしている。僧兵というのは屈強無比の私兵集団であり、これを鎮圧できたことがすでに義家の武力広大を物語っている。また、このころ義家はしばしば鳥羽天皇の行幸の護衛に当たっている。この時代行幸があれば都の人々は道に車を立てて見物するのが習わしであり、それを物見車と言ったが、見物人の主目的はきらびやかに着飾った武士の様子を見ることにあった。おそらくはこの時代の通例となった武士による護衛の様子が人々の興味を集めたもので、勇壮な武士が時代の寵児として迎えられた証左であろう。そしてこの「都の武者」の代表が源氏であり、その主将が義家であった。
やがてまた彼の武将としての威力と評価とをさらに高める機会が到来する。後三年の役である。
京で僧兵対策や天皇警護などに当たっていた彼は、やがて永保三年(一〇八三)、陸奥守兼鎮守府将軍として現地に赴任した。このとき彼は四十五歳。この頃彼の武力の中核は本拠地河内の在地武士よりも、むしろ関東地方の板東武者であったと思われる。彼がそれらの大兵を率いて現地に赴いたとき、偶発的に発生したのが後三年の役であった。
この戦乱は苦戦に次ぐ苦戦の連続であったが、異母弟・新羅三郎義光の助けも得て戦い抜いた義家はかろうじて勝利を収め、彼が助けた藤原清衡による奥州支配の基礎を作ったが、しかし朝廷の停戦命令無視、官物(主に砂金)納入怠慢などの理由から朝廷に私闘と見なされ、何らの恩賞を受けることも出来なかった。義家はやむなく私財をなげうって戦功のあった将士に酬いたが、このことははからずして彼ら板東武者と源氏の頭領との間の私的な主従関係を強める一因となった。
当時中央貴族の庇護を受けるために形式上、田畑を寄進することは一般的であったから、武将として貴族社会に頭角を現した義家にそれを行おうとする各国の在地領主も多くなった。義家も荘園領主とならんとする意思を見せたが、これが白河上皇や上級貴族達を恐れさせ警戒させ、彼らをして源氏抑圧策を取らせるに到った。
白河上皇の源氏抑圧策として、源氏一門の威勢を失墜させるためには一族内部の統制を乱すことと棟梁・義家の権威を損なわせること、そして源氏の経済基盤の拡大を抑えることなどが考えられた。ために義家には後三年の役の論功行賞が行われなかったのみでなく、陸奥守をやめさせられて遂に次の官を与えられることもなかった。また、一族内での争いを助長するために朝廷は義家の同母弟・賀茂次郎義綱を選出して後援、白河上皇の院政以来、義綱の動きはにわかに活発となった。寛治五年(一〇九一)年、両者は河内における郎党相互の抗争から両者は京で合戦を構えた。合戦は関白師実をはじめとした朝廷当局者の働きにより未遂に終わったが、義家のみ諸国からの荘園寄進を禁止され、義綱はかえって朝廷から重きを受ける。
しかし「天下第一の武士」として隠然たる勢力を持つ義家を極度に追い詰めることは得策でなく、承徳二年(一〇九八)年、白河法皇の意向によって陸奥守の功科が認められ、同年院への昇殿を許されて義家は正四位に叙せられ、院の側近となる。これにて一応、義家は上級貴族達と肩を並べることを認められたといえる。
しかし反面、康和三年(一一〇一)に嫡男義親が九州で濫行して翌年隠岐に配流され、嘉承一年(一一〇六)には三男の義国と弟義光が東国で合戦して朝廷から召喚を命ぜられるなど、一族の不祥事が相次ぎ苦境に立たされる中、死亡。源氏の嫡流は四男・義忠が継いだ。権中納言藤原宗忠はその死を悼んで「誠に大将軍に足る」と評したが、のちに「武士の長者として多く罪なき人を殺す」と批評もした。義家は武門の棟梁として大きく評価されるが、その実力には機内周辺を基板とする軍事貴族層が目立ち、諸国の武士の統率者と言うには疑問も残る。また後三年の役以降の不遇も、ことさら公家の抑圧とみることは出来ない。

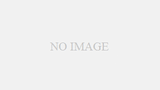
コメント